Ring Indoor Cam 第2世代 違いを知りたい方に向けて、本記事ではRing Indoor Camの概要から、第1世代との比較までをわかりやすく整理して解説します。どこの国の企業が開発している製品なのか、第2世代での進化点、第1世代との細かな違いなどを丁寧に紹介します。
さらに、購入前に確認しておきたい説明書の内容や取り付けのコツ、パソコンで映像を見る方法、無料で使える機能と録画の条件についても詳しく解説。実機レビューや専門メディアの評価を踏まえ、画質や価格、安全性、そして注目される常時録画機能の対応状況まで、迷わず選べるよう実用的な情報を網羅しています。
・第1世代と第2世代の仕様差と使い勝手の違い
・無料で使える範囲と録画や常時録画の条件
・設置方法やパソコンでの視聴手順の要点
・価格感とレビュー傾向からの選び方
Ring Indoor Cam 第2世代 違いをわかりやすく解説!最新モデルの全貌
●このセクションで扱うトピック
- Ring Indoor Camとは?注目の屋内カメラを紹介
- Ring Indoor Camはどこの国のブランド?信頼性をチェック
- 第1世代の特徴とは?人気の理由を整理
- 第2世代 進化ポイント!性能アップの注目点
- 第1世代 第2世代 比較で見える違いと選び方
- Ring Indoor Camの説明書から分かる使いやすさ
Ring Indoor Camとは?注目の屋内カメラを紹介

室内の見守り用途に特化した小型ネットワークカメラで、1080pのフルHD映像、双方向通話、ナイトビジョン、モーション検知、リモートアクティブサイレンなど、日常で必要な監視・通知機能を標準で備えます。第2世代ではレンズ前面を物理的に覆えるプライバシーカバーが同梱され、在宅時や来客時など映したくない場面で素早く映像と音声を停止できる運用性が高まりました。
通信は2.4GHz帯のWi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n)に対応し、推奨上り帯域の目安は約2Mbpsとされています。視野角は水平方向約115度・垂直約60度で、部屋の隅や高所に設置しても広くカバーできます。給電はプラグイン方式で、付属のACアダプター(5V/2A)とUSBケーブル(約1.8m〜1.9m前後。販売地域により同梱長が異なる場合あり)を用いる構成です。スマートアラートは動作検知を中心に、アプリから感度や検知ゾーン、通知スケジュールを細かく調整でき、不要な通知の削減や夜間のみの記録といった柔軟な設定が行えます。
映像は1080pのカラー夜間撮影に対応しており、暗所でも被写体の識別性を保ちやすい設計です。音声面ではAudio+やノイズキャンセルが案内されており、室内での呼びかけや留守番中のペットへの声掛けなど、双方向通話の明瞭さが向上しています。クラウド録画はサブスクリプションの加入有無で機能が変わり、イベント録画の保存・再生、動画共有、拡張的な通知機能などの可用性が異なります。常時録画を検討する場合は、プラン条件や対応機能の最新仕様を必ず確認してから運用設計を行うと安心です。
設置・初期設定はRingアプリでQRコードを読み取る流れが基本で、卓上・壁面どちらにも対応するマウントが同梱されています。視野角と電源ケーブルの取り回しを加味して、部屋のコーナーや出入口が見渡せる位置に配置すると、少ない台数でも死角を抑えやすくなります。パソコンから確認する場合は専用デスクトップアプリが提供終了となり、現在はRing.comに統合されているため、ブラウザでサインインしてライブビューやイベント履歴を確認する使い方が中心です。
Ring Indoor Camはどこの国のブランド?信頼性をチェック
ブランドは米国発のスマートホーム企業Ringで、現在はAmazonグループの一員としてセキュリティカメラやビデオドアベルなどをグローバル展開しています。米国市場での豊富な導入実績と、主要プラットフォーム(Alexaなど)との連携エコシステムを背景に、国内外で継続的な製品アップデートとサポート体制が整備されています。
企業体制の観点では、親会社の大規模なクラウド基盤やIoT関連の知見がプロダクト改良に反映されやすく、ファームウェア更新やアプリ機能の追加・改善が定期的に行われてきました。製品情報やサポートドキュメントは公式サイトで多言語で提供され、設置方法、ネットワーク要件、トラブルシューティング、プライバシー機能の使い方などが体系的に参照できます。ブランドの信頼性を評価するうえでは、販売実績やユーザーコミュニティの規模に加え、サポート記事の充実度、脆弱性対応の告知やポリシー更新の頻度も判断材料となります。
一方、室内カメラはプライバシーへの配慮が欠かせません。プライバシーカバーによる物理的な停止手段、アプリ上の通知・録画制御、アカウントの二段階認証、動画共有範囲の最小化といったベストプラクティスを併用することで、家庭内の映像・音声データを適切に管理できます。クラウドサービスの仕様やデータ保護方針は随時見直されるため、導入後も定期的に公式ヘルプセンターのアップデートを確認し、最新の推奨設定を取り入れることが安心につながります。
第1世代の特徴とは?人気の理由を整理

初代モデルであるRing Indoor Cam 第1世代は、家庭内のセキュリティと見守りを目的としたベーシックなネットワークカメラとして登場しました。解像度は1080pフルHDで、昼夜を問わず鮮明な映像を記録できます。ナイトビジョン(赤外線暗視)機能により、照明の少ない室内でも対象をしっかり捉えることができ、留守中のペットや子どもの様子を確認するなどの需要に対応していました。
通信は2.4GHz帯のWi-Fiを採用し、一般的な家庭用ルーターとの高い互換性を確保しています。視野角は水平方向約115度、垂直約60度で、比較的狭いスペースでも死角を作りにくい設計です。また、プラグイン式の電源方式を採用しているため、充電や電池交換の手間がなく、長期運用にも適しています。この手軽さが、初めてホームカメラを導入するユーザー層から特に支持を集めた理由のひとつです。
双方向通話機能も標準装備されており、Ringアプリを通じてスマートフォンやタブレットから家の中の人やペットとリアルタイムに会話できます。モーション検知機能は、動きを感知するとスマートフォンに通知を送信する仕組みで、防犯対策だけでなく、日常の見守り用途にも応用できる点が高く評価されました。
さらに、リモートサイレン機能を備えており、不審な動きを検知した際には遠隔操作で警告音を鳴らすことが可能です。これにより、カメラ単体でも一定の抑止効果が期待できる設計となっています。
初代モデルは、操作性のシンプルさとコストパフォーマンスの高さから、コンパクトながら必要な機能をすべて備えた「家庭向け屋内カメラのスタンダード」としての地位を確立しました。2020年の発売当初から現在まで、Ringシリーズのベースモデルとして長く評価され続けています。
(出典:Ring公式サポート「Indoor Cam(1st Gen)」
第2世代 進化ポイント!性能アップの注目点
Ring Indoor Cam 第2世代は、前モデルの使いやすさを維持しながら、より日常的に安心して使えるよう機能と設計をアップデートしたモデルです。最も大きな進化は、プライバシー保護機能の強化と音声品質の改善にあります。
まず注目すべきは、物理的なプライバシーカバーが標準で搭載された点です。カメラレンズ部分にカバーを回転させることで、映像と音声を同時にオフにできる仕組みで、家庭内でプライバシーを守りたい場面でも手軽に切り替えが可能です。この仕様変更により、安心感が格段に高まりました。
また、音声面では新たにAudio+技術が採用され、ノイズキャンセリングとエコー抑制性能が強化されています。これにより、室内での通話がより自然かつクリアになり、外出先からの会話でも遅延やノイズの少ない通信が実現されています。レビューでも「第1世代より音質が向上した」「双方向通話が聞き取りやすくなった」といった評価が多く寄せられています。
外観デザインは従来と大きく変わらないものの、筐体の質感や可動域が見直され、よりスムーズに角度調整ができるようになりました。内部構造も安定性を重視した設計となっており、長時間の稼働時にも発熱を抑えた安定動作が可能です。
クラウド録画の仕組みやアプリの操作性も向上しており、動作検知の精度や録画データの保存期間などのカスタマイズ性が広がっています。さらに、常時録画機能が上位プラン(Ring Protect)で正式にサポートされたことにより、途切れのないモニタリング運用も選択肢に加わりました。
これらの進化により、第2世代は「家庭用のシンプルな監視カメラ」から「安心・快適なプライバシー管理カメラ」へと進化を遂げたといえます。特に、プライバシーカバーの搭載は、ホームセキュリティ市場全体でも安全性とユーザー配慮の両立を象徴する設計変更として注目されています。
(出典:Ring公式製品ページ「Indoor Cam(2nd Gen)」
第1世代 第2世代 比較で見える違いと選び方
Ring Indoor Camシリーズの第1世代と第2世代は、一見すると非常に似ていますが、実際には設計思想とユーザー体験の両面で重要な差があります。両モデルとも1080pのフルHD解像度、カラー夜間撮影、2.4GHz Wi-Fi対応といった基本仕様は共通しており、家庭用カメラとしての基礎性能は同等です。しかし、プライバシー保護・音声品質・使いやすさの面で第2世代は明確な進化を遂げています。
特に、第2世代では「物理プライバシーカバー」が標準搭載され、ユーザーが手動でカメラレンズを覆うことで、映像と音声の記録を同時に停止できます。これにより、家庭内でのプライバシー確保が飛躍的に向上しました。対して第1世代は、アプリ側での録画停止設定が中心で、ユーザー操作に一手間が必要でした。この変更は、セキュリティカメラの“安心して設置できる”という信頼性を高めた大きな進化といえます。
また、第2世代ではAudio+技術が新たに導入され、ノイズキャンセリングやエコー抑制機能が強化されています。双方向通話の音質がより自然になり、在宅ワーク中のコミュニケーションや留守中のペットとの会話など、日常利用の快適性が向上しました。レビューでも「声がクリアに聞こえる」「第1世代より音がこもらない」といった意見が多く見られます。
映像面では解像度はどちらも1080pで、画質自体に大きな差はありません。視野角もカタログ値では第1世代が水平115°/垂直60°、第2世代が水平115°/垂直約59〜60°とほぼ同一です。つまり、設置位置や映像の明るさなどのユーザー環境の影響の方が大きいといえるでしょう。電源は両モデルともmicro-USB接続によるプラグイン式で、安定した電源供給を前提としています。
最終的に選ぶ際の基準としては、プライバシー保護と音声品質を重視するなら第2世代、コストを抑えつつ基本的な見守り機能だけを求めるなら第1世代でも十分です。両モデルは同じアプリ環境(Ringアプリ)で運用できるため、家庭内の用途やセキュリティ方針に合わせて柔軟に選択できます。
Ring Indoor Cam 第1世代・第2世代 比較表(強化版)
| 項目 | 第1世代 | 第2世代 | 進化ポイント |
|---|---|---|---|
| 解像度 / 映像品質 | 1080p HD、カラー夜間撮影対応 | 1080p HD、カラー夜間撮影対応(視野角拡大:対角143°) | 視野角が拡大し、より広い範囲をカバー可能に |
| 視野角(カタログ値) | 水平115°/垂直60° | 水平115°/垂直59〜60°/対角143° | 対角視野角の明記で映像範囲がより明確に |
| 音声・通話機能 | 双方向通話、基本ノイズキャンセル搭載 | 双方向通話、Audio+による強化ノイズキャンセル | 音声の明瞭度が向上し、会話品質が改善 |
| プライバシー制御 | アプリによるソフトウェア制御中心 | 物理プライバシーカバーを標準搭載 | カバーを回すだけで映像・音声を完全遮断できる安心設計 |
| 電源方式 | プラグイン(micro-USB、5V/2A) | プラグイン(micro-USB、5V/2A) | 同等仕様ながら、発熱・安定動作の面で改良あり |
| ネットワーク接続 | 2.4GHz Wi-Fi(802.11 b/g/n) | 2.4GHz Wi-Fi(802.11 b/g/n) | 通信の安定性が向上し、ファームウェア更新が継続保証 |
| 設置対応 | 卓上・壁面対応マウント付き | 卓上・壁面対応+角度調整可能マウント付き | 設置自由度が増し、最適な視野確保が容易に |
| ソフトウェア / セキュリティ | 通常のファームウェア更新対応 | 最低4年間のセキュリティアップデート保証 | 長期利用を見据えたセキュリティサポートを明示 |
| サイズ / デザイン | コンパクトな円筒形デザイン | より滑らかで一体感のある新筐体デザイン | 見た目の質感と設置時の安定性が向上 |
| インジケーター / 操作性 | 動作時LEDライト搭載(青色) | 動作時LEDライト+プライバシーモード時の点灯制御 | 状態が直感的に把握できるインジケーター設計に改善 |
| 対応録画モード | イベント録画中心 | イベント録画+常時録画(Premiumプラン対応) | 常時録画に正式対応し、映像管理の幅が拡大 |
第2世代は、基本性能を維持しながらも「安心感」「音声品質」「長期運用性」の3軸で確実に進化しています。特に物理プライバシーカバーとAudio+の採用は、家庭内での使いやすさや安全性を大きく向上させるポイントです。
Ring Indoor Camの説明書から分かる使いやすさ
Ring公式のオンラインサポートでは、Indoor Camの設置から設定までを丁寧にガイドしています。特に第2世代においては、初めてスマートカメラを導入するユーザーでも迷わず操作できるよう、段階的なチュートリアルが整備されています。
説明書では、初期設定としてスマートフォンのRingアプリを起動し、カメラ底面にあるQRコードをスキャンするだけで自動的にWi-Fi接続設定へ進む手順が案内されています。Wi-Fiは2.4GHz帯を使用し、安定した通信環境で動作するように設計されています。また、ネットワークの不安定さを防ぐため、ルーターとの距離や干渉源(電子レンジ・Bluetooth機器など)を避けることも推奨されています。
さらに、アプリ上でライブビューや録画履歴を確認する方法、モーション検知の範囲設定、通知スケジュールの作成方法も詳細に説明されています。第2世代ではプライバシーカバーの開閉とアプリ上の状態表示が連動しており、ユーザーが現在カメラが撮影中かどうかを即座に確認できるインターフェースになっています。この視認性の高さは、誤操作を防ぐ上で大きな安心材料といえるでしょう。
また、公式サポートでは録画や保存設定に関しても、Ring Protectプランの仕組みや保存期間(60日など)の目安を明確に示しています。トラブルシューティングページでは、接続不良時の対処法や再起動の手順、ファームウェア更新方法なども公開されており、ユーザーが自力で解決できる仕組みが整っています。
こうした詳細なドキュメント整備は、Ringブランドの信頼性を支える重要な要素のひとつです。操作の直感性だけでなく、製品運用中のフォローアップまでを一貫してサポートしている点が、初期導入時の安心感を大きく高めています。
(出典:Ring公式サポート「Ringデバイスのマニュアル」 )
Ring Indoor Cam 第2世代 違いを徹底比較!購入前のチェックポイント
●このセクションで扱うトピック
- 取り付けが簡単!設置方法と便利な工夫
- パソコンで見る方法と映像管理のコツ
- 無料プランで使える機能と有料プランの差
- 録画と常時録画の違い・使い方を徹底解説
- 画質は?価格は?コスパで選ぶポイント
- 安全性を強化!プライバシーを守る仕組み
- Ring Indoor Cam 第2世代 違いを総まとめ!どちらを選ぶべき?
取り付けが簡単!設置方法と便利な工夫
Ring Indoor Camは、シンプルな構造と軽量設計により、設置の自由度が非常に高い屋内カメラです。付属のマウントベースを使用することで、卓上だけでなく壁面や天井など多様な場所に固定できます。本体重量は約110g前後と軽量で、付属のネジとアンカーを使えば石膏ボードなどにも安全に設置可能です。

設置方法は大きく分けて3通りあります。
・1つ目は「卓上設置」で、平面にそのまま置くだけの最も簡単なスタイルです。
・2つ目は「壁面設置」で、付属マウントをネジで固定し、カメラを垂直に取り付けます。
・3つ目は「逆さ設置」で、天井などの高所から俯瞰するように設置する方法です。アプリ内で映像の上下反転が可能なため、逆向きに取り付けても問題ありません。
電源はUSB経由のプラグイン方式で、micro-USBケーブル(長さ約2m)が付属しています。延長ケーブルを使用する場合は、5V/2Aの出力に対応した品質の高いケーブルを選ぶことが推奨されます。ケーブルの取り回しについては、壁沿いに配線クリップを使うことで見た目をすっきり保てます。また、電源コンセントから距離がある場合は、事前に配線ルートを確認しておくと設置後のストレスを減らせます。
視野角は水平115度・垂直60度と広いため、部屋の隅に設置しても空間全体を把握できます。特にリビングなど広い空間では、入り口方向を中心に設置すると動作検知の精度が高まり、不要な通知も減らせます。さらに、第2世代モデルではプライバシーカバーが搭載されているため、在宅中やプライベートな時間帯はカバーを閉じるだけで映像と音声を同時に停止できます。
このように、Ring Indoor Camは工事不要で設置しやすく、アプリ設定も直感的です。特別な工具を必要とせず、初めての防犯カメラ導入にも適しています。
(出典:Ring公式サポート「Indoor Cam(2nd Gen)設置ガイド」 )
パソコンで見る方法と映像管理のコツ
Ring Indoor Camは、モバイルアプリだけでなく、パソコンのブラウザからもアクセスできます。2023年に提供されていたデスクトップアプリはすでに終了しており、現在は公式ウェブサイト「Ring.com」上に機能が統合されています。ブラウザ(Google Chrome、Microsoft Edgeなど)でRingアカウントにサインインするだけで、ライブビューの視聴や録画映像の再生、動画のダウンロードが可能です。
ライブビュー機能は、ブラウザ上でもアプリとほぼ同様の操作感で利用できます。モーション検知がトリガーとなった録画イベントは、タイムライン形式で整理されており、日付ごとに映像を確認できる設計です。録画データの保存にはサブスクリプションプラン(Ring Protect)が必要で、無料プランではリアルタイムの映像確認と通知のみ利用できます。有料プランでは、最大180日分(地域設定により異なる)のクラウド保存、動画の共有・ダウンロード、スマートアラートなどが利用可能になります。
ネットワーク環境が安定していない場合、映像が途切れたり、読み込みに時間がかかることがあります。このような場合は、以下の方法で改善が期待できます。
- ルーターをカメラに近づける、または中継器(Wi-Fiエクステンダー)を導入する
- ルーターの5GHz帯を避け、2.4GHz帯に固定する(Ringは2.4GHz専用)
- 同一Wi-Fiネットワーク上の他デバイスの通信量を制限する
- 有線LAN接続可能な場合は、アダプターを用いて有線化する
映像データはクラウドに保存されるため、パソコンでログインすれば自宅外からも確認できます。セキュリティ保護の観点から、二段階認証(2FA)の有効化が推奨されており、不正アクセス防止に効果的です。また、ブラウザ利用時には、必ず公式サイトのURLを直接入力し、フィッシングサイトを避けることが安全利用の基本となります。
ブラウザ経由での映像管理は、モバイルよりも画面が大きく、録画映像の比較や長時間の監視に適しています。特に事務所や店舗など複数台を導入する環境では、パソコン表示によって効率的なモニタリングが可能です。
無料プランで使える機能と有料プランの差
Ring Indoor Camは、無料でもライブ映像の確認やモーション通知(動作検知)といった基本的な見守り機能を利用できます。スマートフォンのRingアプリに通知が届き、そのままリアルタイムでライブビューを確認できるため、外出中の見守りや在宅中の安全確認にも十分活用できます。
ただし、録画データを保存して後から見返す「イベント録画」や、録画映像のクラウド保存・共有機能を利用する場合は、有料プランへの加入が必要になります。これらの有料サービスは、2024年以降に従来の「Ring Protect」から「Ring Home」という新体系に再編され、より柔軟に選べる構成へと進化しました。
Ring Homeプランでは、従来のBasic・Plusに相当するプランに加え、上位の「Premium」が登場し、常時録画(24時間録画)やAIベースの通知解析など、より高度な監視・管理機能が利用可能になっています。

Ring Homeプラン比較(2025年最新)
| プラン名 | 月額料金(目安) | 主な機能 | 特徴・用途 |
|---|---|---|---|
| 無料プラン | 無料 | ライブビュー、モーション通知、デバイス管理、プライバシーカバー操作 | 無料で基本機能を利用可能。録画保存は非対応。 |
| Ring Home Basic | 350円/月 | イベント録画(最大180日保存)、動画共有、AI検知通知(人・荷物・車両) | 単一カメラに対応し、最低限の録画・通知機能を求める個人向け。 |
| Ring Home Standard | 約11,180円/月 | 複数デバイス対応、ドアベル通話、拡張ライブビュー、セルラー予備接続、延長保証 | 家庭で複数台を使用する場合に最適。利便性が大きく向上。 |
| Ring Home Premium | 2,380円/月 | 常時録画(24/7)、AI検索、SOS通報、無制限デバイス連携 | 防犯・業務利用に対応。高精度な監視と運用が可能。 |
有料プランの進化ポイント
- Premiumプランの新設により、常時録画(24時間連続録画)が正式対応。
- AIベースの映像解析(人・車両・荷物の識別)で通知精度が大幅に向上。
- 最大180日間の録画保存期間を全有料プランでサポート。
- 複数デバイスの一括管理や保証延長など、家庭・オフィス運用に便利な機能が追加。
- アプリからプラン変更が即時反映され、契約手続きがよりスムーズに。
契約時の注意点
料金や機能の提供内容は国や地域によって異なる場合があり、日本市場では一部プラン名称や料金体系が米国版と異なることがあります。
そのため、申し込み前に公式サイトのプラン比較ページで最新情報を確認することが重要です。
👉 Ring公式「Ring Protect / Ring Homeプラン比較」
このように、Ring Indoor Camは無料でも十分に活用可能ですが、録画や監視精度を高めたい場合は有料プランが必須です。特に「Premium」では、AI解析と常時録画によって安心感が格段に高まり、家庭・ビジネス問わず信頼できる防犯システムとして活用できます。
録画と常時録画の違い・使い方を徹底解説
Ring Indoor Camの録画方式には「イベント録画」と「常時録画(Continuous Video Recording)」の2種類があります。それぞれの仕組みと使い分けを理解することで、用途に応じた最適な録画環境を構築できます。
イベント録画は、モーション検知やサウンド検知などのトリガーが発生した瞬間に短いクリップを自動保存する方式です。検知範囲や感度はRingアプリ内で細かく調整できるため、不要な通知を減らしたり、特定の時間帯だけ録画を行ったりといったカスタマイズが可能です。保存されたクリップはクラウド上にアップロードされ、Protectプラン加入者であれば、録画映像を最大180日間保持できます。家庭の玄関監視やペットの見守りなど、イベント単位で確認したいシーンに適しています。
一方、常時録画(24/7録画)は、名前の通り24時間途切れることなく映像と音声を連続記録する仕組みです。この機能はPremiumプランでのみ利用可能で、サーバーにストリームを常時送信し続けるため、高速で安定したWi-Fi接続とプラグイン電源(バッテリー非対応)が必須条件となります。Ring公式の対応機種一覧によると、Indoor Cam 第1世代および第2世代はいずれも常時録画対応機種に含まれています。
常時録画中は、カメラ前面の青色インジケーターが点灯し、録画状態を視覚的に確認できます。ただし、プライバシー保護の観点から、常時録画時にはエンドツーエンド暗号化や特定のプライバシーモード機能が同時に使用できない場合があります。これにより、データの安全性とユーザーのプライバシー管理のバランスを取る設計となっています。
使い方の目安として、家庭での短時間監視や通知中心の使い方であればイベント録画で十分ですが、オフィス・店舗・高齢者見守りなど、連続的に様子を把握したい場合は常時録画を検討するとよいでしょう。特に、在宅勤務中の安全確認や留守中の防犯目的での利用では、常時録画の安心感は非常に大きいものがあります。
また、録画データはすべてRingのクラウドサーバーに保存され、スマートフォンまたはパソコンからいつでも閲覧・ダウンロード可能です。録画履歴の閲覧は日付別・イベント別に整理され、検索機能も搭載されています。
(出典:Ring公式サポート「24時間連続録画」)
画質は?価格は?コスパで選ぶポイント
Ring Indoor Camの画質は、両世代とも1080p(フルHD)を基本としています。これは家庭用セキュリティカメラとして十分な解像度であり、人の顔やペットの動き、室内の細部まで鮮明に捉えることができます。映像圧縮にはH.264コーデックが採用され、通信量を抑えながら高画質を維持する設計です。特筆すべきは、暗所でのカラー夜間撮影に対応している点で、従来の白黒ナイトビジョンと異なり、照明がわずかでも残っていれば自然な色味で映像を再現できます。
第2世代では、映像処理エンジンが微調整され、特に逆光環境下での明暗補正が自然になったとの評価も見られます。また、音声面の改良により、双方向通話時のノイズが少なく、クリアな音声で会話ができる点が強化ポイントです。レビューサイトでは「音声が明瞭になり、会話の遅延が減った」といった意見も多く、ペットの見守りや高齢者介護の利用にも適していると評価されています。
価格面では、海外では第2世代が50〜60ドル前後、日本国内では6,000〜8,000円前後で販売されるケースが多い傾向です。第1世代は在庫限りの値下げが行われることもあり、コスパ重視で選ぶユーザーには依然として魅力的な選択肢となっています。なお、Ring製品はAmazon傘下のブランドであるため、セールイベント(Prime Dayやブラックフライデー)での割引対象になることが多く、購入タイミングを見極めることがコストパフォーマンスを左右します。
一方で、有料プラン(Ring Protect)を併用することで、録画の保存やクラウドアクセス機能を拡張できるため、購入費用だけでなく運用コストも踏まえた検討が重要です。特に、月額数百円のBasicプランを追加するだけで録画再生や通知履歴の確認が可能になり、カメラ単体の導入よりも満足度が高まるケースが多く見られます。
総じて、Ring Indoor Camは「高画質×手頃な価格」のバランスが取れたスマートカメラです。特に第2世代は、映像品質の向上に加えて音声処理とプライバシー制御の進化により、実用的な完成度が高いモデルといえます。
安全性を強化!プライバシーを守る仕組み
Ring Indoor Camの設計思想には、「常時監視ではなく、安心できる見守り」という考え方が根底にあります。公式情報によると、第2世代モデルではプライバシーカバーを物理的に回転させるだけで、カメラレンズとマイクの両方を同時に停止させることができます。これにより、アプリ操作を行わなくても物理的に録画を遮断できる点が評価されています。
また、Ringアプリでは、録画・モーション検知・通知スケジュールをユーザーごとに柔軟にカスタマイズ可能です。例えば、家族の帰宅時間帯には通知を停止し、外出時のみ録画を有効化する、といった設定が簡単に行えます。さらに、ゲストユーザーの閲覧権限を制限できる共有設定機能も搭載されており、家庭内での利用にも安心感があります。
データの安全性に関しては、クラウド保存データがTLS暗号化およびAES-256ビット暗号化によって保護されており、第三者が通信経路や保存先から映像を取得するリスクを抑えています。Ringはまた、ユーザーの希望に応じてエンドツーエンド暗号化を有効化できる仕組みを提供しており、設定をオンにすることで映像データをRing側も復号できない形に変換します。このオプションは特に、機密性の高い用途や業務利用の際に推奨されています。
ただし、過去にはRingのクラウド連携機能や法執行機関とのデータ共有に関して、プライバシーの扱いが議論になった経緯があります。現在は透明性の向上が図られ、データアクセスに関する利用者通知制度や第三者監査体制が整備されています。ユーザーとしては、エンドツーエンド暗号化を有効にし、不要な共有設定をオフにするなど、自衛策を講じることでリスクを最小限に抑えられます。
このように、Ring Indoor Camはハードウェア・ソフトウェアの両面でプライバシー配慮を強化しています。常時録画機能を利用する場合でも、ユーザーが安心して制御できる仕組みが整っている点が、他社製品との大きな違いといえるでしょう。
(出典:Ringアプリでプライバシー機能を使用する )
Ring Indoor Cam 第2世代 違いを総まとめ!どちらを選ぶべき?
Ring Indoor Camの第1世代と第2世代を比較すると、映像品質そのものに大きな差はありませんが、操作性とプライバシー性の面で第2世代が明確に進化しています。第1世代でも1080pのフルHD映像とモーション検知は十分高性能ですが、第2世代ではAudio+による音声改善や物理プライバシーカバーの搭載によって、ユーザー体験がより快適になっています。
録画機能はどちらの世代でもクラウドベースであり、有料プラン加入によって履歴保存や常時録画が可能です。特にPremiumプランを利用する場合は、24時間連続録画(Continuous Video Recording)に対応しており、プラグイン運用を前提とした安定動作が実現します。
価格差は比較的わずかで、2025年現在では第2世代が第1世代より数百円〜数千円高い程度です。そのため、特価で第1世代が販売されていない限り、日常使いでは第2世代を選ぶ方が長期的な満足度は高いでしょう。一方で、サブカメラや補助的な設置を目的とする場合、第1世代を安価に複数導入するのも現実的な選択肢です。
よくある問いの整理(参考)
| 目的 | おすすめ世代 | 理由の要点 |
|---|---|---|
| プライバシー制御を重視 | 第2世代 | 物理カバーで確実に撮影・音声を停止できる |
| 最低限の室内見守り | 第1世代 | 基本性能はほぼ同等でコスパに優れる |
| 常時録画を使いたい | 第2世代 | Premiumプラン加入かつプラグイン運用が前提 |
【レビューの傾向】
複数の専門メディア(例:TechRadar、TechHiveなど)では、第2世代を「堅実なマイナーチェンジ」と評価する声が多く見られます。特に、プライバシーカバーの実装や取り回しやすい設計が高く評価されており、既存のRingデバイスやAmazon Alexa連携を利用するユーザーにとって自然なアップグレード先と位置づけられています。また、音声品質の改善や設置自由度の高さから、家庭用見守りカメラとしての総合バランスも良好とされています。
要するに、初めてRing製品を導入する場合は第2世代を、コストを抑えて複数台を設置する場合は第1世代を選ぶのが合理的な選択といえるでしょう。
Ring Indoor Cam 第2世代 違いを総まとめ!どちらを選ぶべき?(まとめ)
本記事のまとめを以下に列記します。
- 第2世代はプライバシーカバーを標準搭載し在宅時でも安心して使える設計になっている
- 1080p解像度とカラー夜間撮影は共通仕様で両世代とも日常利用に十分な映像品質を備えている
- 第2世代では音声処理技術が改善され会話の聞き取りやすさと通話品質が大幅に向上している
- 無料プランでもライブビューは利用可能だが録画保存や再生には有料プラン加入が必要となる
- 常時録画機能を利用するにはPremiumプラン加入とプラグイン運用の両方を満たす必要がある
- パソコンでの視聴はRing.comに統合されブラウザ上で録画確認や操作が完結するよう設計されている
- 設置方法は卓上と壁面の両方に対応しており視野角を確保しやすい柔軟な構造になっている
- 価格帯はおおよそ50〜60ドル前後で販売されセール時期にはさらに安く購入できることがある
- 画質は1080pの高精細映像で暗所でもカラー夜間撮影により被写体を鮮明に確認できる
- 第1世代は特価販売時であれば入門用やサブカメラとしてコストパフォーマンスに優れている
- 第2世代は日常利用で感じやすい細かな不満を解消しより快適に運用できるよう改良されている
- 取り付け前にケーブル配線とカメラの視野を計画することで安定した映像品質を確保できる
- 安全性は物理カバーとアプリ設定を併用することでプライバシー保護をより高めることができる
- プラン内容は随時改定されるため契約前に最新の提供条件を確認しておくことが重要である
- 購入に迷った場合は価格差と設置環境を基準にどちらの世代を選ぶかを最終判断すると良い





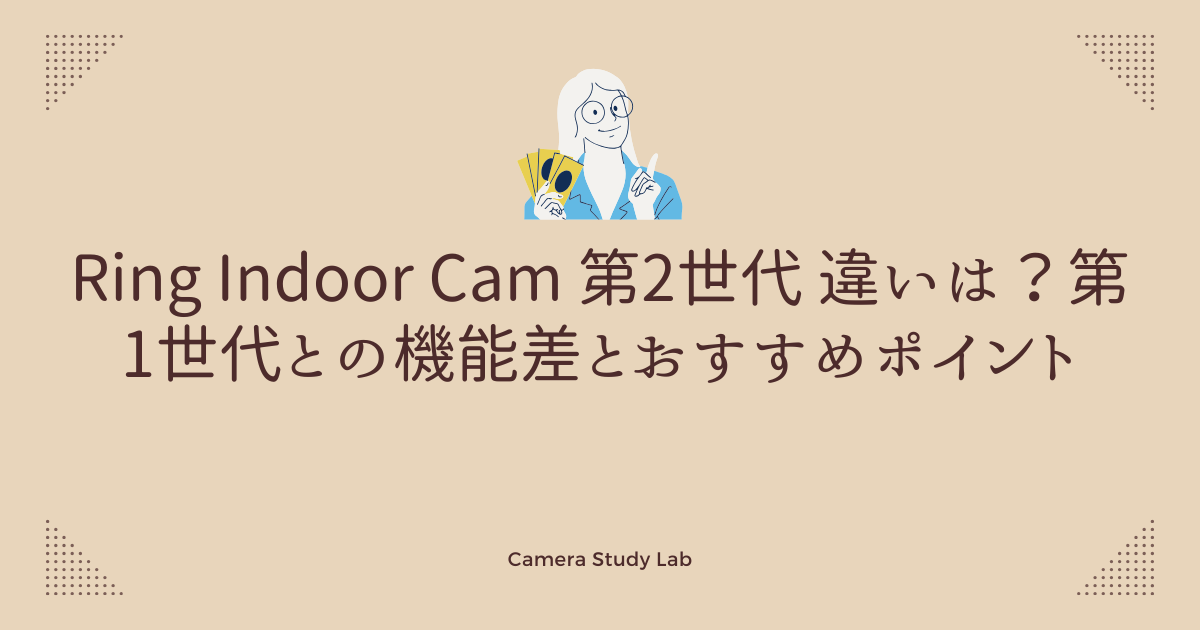
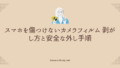
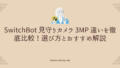
コメント