ニコンの人気APS-Cミラーレスカメラ「Z50」に続く新モデルの登場により、多くのユーザーが「ニコン z50後継機」の情報を探しています。本記事では、Z50とその後継機Z50IIの違いや進化点をわかりやすく比較し、どちらが自分に合っているのかを判断しやすく整理しています。
また、ニコン z50後継機を最大限に活用するためのおすすめアイテムや神レンズも厳選紹介。さらに、中古市場でZ50を検討している方にも役立つ情報をまとめました。カメラ選びで後悔しないために、これからZ50IIを購入したい人、Z50から乗り換えるか迷っている人、Z50を今から中古で手に入れようと考えている人にとって、必見の内容となっています。
- ニコン z50後継機(Z50II)の進化ポイントとスペック比較
- 撮影スタイル別に最適なおすすめアクセサリーの選び方
- Z50IIと相性の良い最新レンズや便利アイテムの特徴
- 旧モデルZ50との違いや乗り換え判断の基準
ニコン Z50後継機の実力と進化を徹底解説
ミラーレス一眼カメラ「ニコン Z50」は、2019年に登場して以来、軽量で高画質なAPS-C機として多くの支持を集めてきました。小型ながらも高い描写力を誇り、日常撮影やVlog、旅行用途まで幅広く対応できるエントリーモデルとして人気を博しました。そして2024年、ついにその後継機「Z50II」が登場。処理性能や動画機能、AF精度などあらゆる面で進化を遂げたZ50IIは、Z50ユーザーのみならず新たにカメラを始めたい層にも注目されています。
本記事では、Z50とZ50IIそれぞれの特徴・違い・選び方について詳しく解説します。
Z50とはどんなカメラ?特徴を紹介

ニコン Z50は、2019年11月に発売されたAPS-Cサイズ(DXフォーマット)センサーを搭載するミラーレス一眼カメラです。ニコン初のAPS-Cミラーレスとして登場し、Zマウントシステムを採用しています。
このカメラの最大の特徴は、小型軽量ながら高い描写性能を持ち合わせている点です。ボディ単体の重さは約395g(バッテリー・メモリーカード込みでも約450g)で、長時間の持ち運びにも向いています。グリップも深めに設計されており、ホールド性にも優れています。
主なスペック一覧(ニコン Z50)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| センサー | APS-Cサイズ CMOSセンサー(23.5×15.7mm) |
| 有効画素数 | 約2088万画素 |
| 画像処理エンジン | EXPEED 6 |
| ISO感度 | ISO 100〜51200(拡張で204800相当) |
| 連写性能 | 約11コマ/秒(高速連続撮影時) |
| オートフォーカス | ハイブリッドAF(209点) |
| 動画撮影 | 4K UHD(30p)、フルHD(120p対応) |
| 液晶モニター | 3.2型 約104万ドット チルト式タッチパネル |
| ファインダー | 約236万ドット OLED電子ビューファインダー |
| 記録メディア | SDカード(UHS-I対応) |
| バッテリー寿命 | 約300枚(CIPA基準) |
| サイズ | 約126.5×93.5×60mm |
| 重量 | 約395g(本体のみ) |
Z50の画質面では、有効2088万画素のAPS-Cセンサーにより、自然なボケ感と高解像度な描写が得られます。JPEG撮って出しでも発色が美しく、編集の手間をかけずに満足できる画を得ることが可能です。
AF性能についても、209点のハイブリッドAFシステムにより、被写体の検出と追従がスムーズです。特に顔認識AFや目AF(Eye-Detection AF)は、ポートレートやVlog用途に重宝します。
動画機能も優れており、クロップなしの4K 30p撮影に対応しています。加えて、フルHDでは120fpsのスローモーション撮影も可能なため、映像表現の幅が広がります。
ただし、ボディ内手ブレ補正(IBIS)は搭載されていないため、手ブレ対策としてはVR(手ブレ補正)搭載レンズの使用が前提となります。夜景や望遠撮影などでは三脚や手ブレ補正付きレンズの併用をおすすめします。
このように、ニコン Z50は軽さ・価格・性能のバランスに優れたエントリーミラーレス機です。初めてのミラーレス一眼を探している方、または旅行やVlog向けの高画質カメラを検討している方にとって、有力な選択肢といえるでしょう。
Z50の後継機 Z50IIについて

Z50IIは、ニコンが2024年11月に正式発表・発売したZ50の正統な後継モデルです。前機種の特長を踏襲しつつ、性能や機能面において大幅な進化を遂げています。特に連写性能やAF精度、動画機能の強化が目立ち、静止画と動画のどちらにも本格的に取り組みたいユーザーに適しています。
●まず大きな変化として、画像処理エンジンが「EXPEED 6」から「EXPEED 7」へと進化しています。これにより、処理速度が約10倍に高速化され、連写性能は最大30コマ/秒を実現しました。さらに「プリリリースキャプチャ」機能を使えば、シャッターを押す前の瞬間までさかのぼって記録できるため、一瞬のチャンスを逃しにくくなっています。
●また、AF機能も大幅にアップデートされており、9種類の被写体認識(人物・犬・猫・鳥・車など)に対応しています。これにより、動きの速い被写体でも高精度にフォーカスを合わせられるようになりました。Z50では一部にあった「追従性能の物足りなさ」が解消されたといえるでしょう。
●動画性能の面でも進化は明確です。Z50IIは4K/60pに対応しており、映像は5.6Kオーバーサンプリングによる高精細な記録が可能です。加えて10bit H.265、N-Log、HLGなどの記録方式に対応しているため、本格的な映像制作にも十分活用できます。これまでZ50では制限されていたプロフェッショナル向け設定が、Z50IIでは標準搭載されています。
●その一方で、ボディ内手ブレ補正(IBIS)は引き続き非搭載のままです。そのため、手ブレに関してはレンズ側の補正機能や三脚などの機材で対応する必要があります。これは軽量化とコストバランスを重視した設計のためと考えられます。
●さらに便利になった点として、USB-Cによる給電やファームウェアアップデートの対応、スマートフォン連携アプリ「SnapBridge」との親和性向上など、日常的な運用にも配慮されています。
●価格面では、Z50IIボディ単体で約14万円前後、レンズキットは約16万円前後で販売されています(市場状況によって変動あり)。Z50よりもやや価格は上がりますが、その分の機能向上は十分に納得できる内容です。
このように、Z50IIはZ50の使いやすさと軽量性を受け継ぎながらも、性能面で大きく飛躍した後継モデルです。日常撮影から本格的な動画制作まで幅広く対応できるため、初心者からステップアップを目指すユーザーにとって有力な選択肢といえるでしょう。
Z50とZ50IIの比較:どちらがおすすめかを分析
Z50とZ50IIを比較する際、選ぶべき基準は「価格」「撮影目的」「スペックの優先度」にあります。それぞれの特長を理解することで、自分に合った1台を選びやすくなります。
●まずZ50は、軽量コンパクトでコストパフォーマンスに優れており、初めてミラーレスカメラを使う方や、日常のスナップ撮影、旅行用として気軽に使いたい方に最適です。ボディの重さは約450gと軽く、カメラバッグに入れても負担が少ないのが魅力です。また、有効2088万画素のAPS-CセンサーとEXPEED 6エンジンにより、自然な色味と描写力が得られます。
一方でZ50IIは、処理性能と連写速度において大きく進化しています。画像処理エンジンが最新の「EXPEED 7」となり、処理速度はZ50比で約10倍に向上。連写性能も最大30コマ/秒に対応し、スポーツや動体の撮影において明確なアドバンテージがあります。さらに、シャッターボタンを押す前から記録できる「プリリリースキャプチャ」機能も搭載されており、一瞬のシャッターチャンスにも強くなっています。
●AF機能の進化も注目すべき点です。Z50は209点のハイブリッドAFを採用していますが、Z50IIではさらに9種類の被写体認識(人・犬・猫・鳥・車・バイクなど)に対応しています。このため、人物撮影やペット撮影を多用するユーザーにとっては、Z50IIのほうが安心して使えるでしょう。
●動画機能に関しても、Z50IIは本格的な撮影を見据えた設計になっています。4K/60p記録、5.6Kオーバーサンプリング、10bit H.265、N-Log、HLGなど、より高画質かつ編集しやすい映像が撮れる環境が整っています。Z50では4K/30p止まりだったため、動画制作を中心に考える場合はZ50IIが明確に優位です。
ただし、Z50IIにも注意点があります。IBIS(ボディ内手ブレ補正)は非搭載のままで、Z50と同様にレンズ側の手ブレ補正や三脚が必要です。また、本体重量は約495gとZ50より約45g重くなっており、携帯性重視の方は気になるかもしれません。
●価格面では、Z50が現時点で実売8万円前後(中古であればさらに安価)、Z50IIはボディ単体で約14万円と、コスト差が大きくなっています。コスパを重視するならZ50、性能と将来性を重視するならZ50IIという選び方が基本になります。
このように考えると、Z50は「必要十分な性能をお得に手に入れたい人」に、Z50IIは「動体・動画・将来性にこだわる人」に向いています。予算と目的に応じて選ぶことが、最も納得のいく選択につながるでしょう。
●Z50とZ50IIのスペック比較
| 項目 | Z50 | Z50II |
|---|---|---|
| 発売時期 | 2019年11月 | 2024年11月 |
| センサー | APS-C CMOS(23.5×15.7mm) | 同左 |
| 有効画素数 | 約2088万画素 | 同左 |
| 画像処理エンジン | EXPEED 6 | EXPEED 7 |
| ISO感度 | ISO 100〜51200(拡張204800) | 同左 |
| 連写性能 | 約11コマ/秒 | 最大30コマ/秒(プリキャプチャ対応) |
| オートフォーカス | 209点ハイブリッドAF | 209点+被写体認識AF(9種) |
| 動画性能 | 4K/30p・FHD/120p | 4K/60p(10bit・N-Log対応)・FHD/120p |
| ファインダー | 0.39型OLED 約236万ドット | 輝度向上・同解像度 |
| 液晶モニター | 3.2型 約104万ドット チルト式 | 同左(高耐久加工) |
| 手ブレ補正 | 非搭載 | 非搭載 |
| 対応バッテリー | EN-EL25 | EN-EL25a(USB-C給電・充電対応) |
| サイズ | 約126.5×93.5×60mm | 約126.5×96.8×66.5mm |
| 重量(バッテリー含む) | 約450g | 約495g |
| その他特徴 | – | プリセット色設定(Imaging Recipe)、商品レビューモード、USB-C電源対応 |
価格面では、Z50IIボディ単体で約14万円前後、レンズキットは約16万円前後で販売されています(市場状況により変動あり)。Z50よりもやや価格は上がりますが、その分の機能向上は十分に納得できる内容です。
このように、Z50IIはZ50の使いやすさと軽量性を受け継ぎながらも、性能面で大きく飛躍した後継モデルです。日常撮影から本格的な動画制作まで幅広く対応できるため、初心者からステップアップを目指すユーザーにとって、有力な選択肢といえるでしょう。
ニコンZ50II レビュー 評判から見る評価とは
Z50IIは、Z50の後継機として2024年に正式登場して以来、静止画と動画の両面で大きな注目を集めています。レビューや評価を見ていくと、処理性能・連写性能・AF精度・動画機能の進化が高く評価されている一方で、価格や一部未対応機能についてはやや意見が分かれる印象です。
■ 良い点(高評価されたポイント)
- 画像処理エンジンがEXPEED 7に進化し、処理速度がZ50比で約10倍に向上
- 最大30コマ/秒の高速連写と「プリリリースキャプチャ」機能で決定的瞬間に強い
- 9種類の被写体認識AF(人物・動物・車など)により追従精度が向上
- 4K/60p対応、10bit H.265、N-Log、HLG記録により動画性能が大幅に強化
- 商品レビューモード搭載でYouTuberやクリエイターにも使いやすい
- 「Imaging Recipes」などプリセット表現機能が充実し、カラー表現の幅が広い
- USB-C給電・充電対応で動画撮影や配信にも便利
- バリアングル液晶・タッチ操作でVlog撮影に適している
■ 悪い点(懸念・指摘されているポイント)
- ボディ内手ブレ補正(IBIS)は非搭載で、手持ち撮影にはレンズ側の補正が必要
- 本体重量が約495gとZ50より重く、携帯性でやや不利
- 価格が実売で約14万円〜とやや高めで、上位機種(Z5/Z6II)と競合する可能性あり
- バッテリー性能は据え置きで、長時間の撮影には予備バッテリーが必要
このように、Z50IIは特にAFと動画撮影で高い評価を受けている一方で、価格と手ブレ補正の面で慎重な検討が必要です。用途に合わせた比較が購入のポイントになります。必要であればZ50との項目別比較も作成できます。
Z50/Z50II 画質の違いをわかりやすく解説
Z50とZ50IIの画質については、同じAPS-Cセンサーを前提としつつも、画像処理エンジンの進化による差が出る可能性があります。Z50はEXPEED 6を搭載していますが、Z50IIでは最新のEXPEED 7が搭載される可能性があります。
この進化により、ノイズ処理や色再現、階調表現において目に見える差が生まれると考えられます。特に高感度撮影時の画質向上が期待されており、夜間や暗所での撮影シーンでその差が現れやすいでしょう。
ただし、Z50の画質も現状で十分に高水準です。よほど細部にこだわるケースや、大型プリント出力を前提としない限り、日常の撮影で大きな違いを感じにくい可能性もあります。




Z50からZ50IIへの乗り換えはどんな人に向いているか?
Z50からZ50IIへの乗り換えは、撮影の幅を広げたい人や、性能に物足りなさを感じてきた人にとっては、明確なメリットがあります。特に以下のような用途であれば、Z50IIに乗り換える価値は十分にあるといえるでしょう。
まず、動きの速い被写体を撮影する機会が多い方です。Z50IIは、最大30コマ/秒の高速連写やプリリリースキャプチャ機能を備えており、一瞬のタイミングを確実に捉えやすくなっています。スポーツ、ダンス、子どもの運動会、動物など、反応速度が求められる撮影シーンでは、Z50との違いをはっきりと実感できるはずです。
また、YouTubeやVlogなど動画撮影を本格的に行いたい方にもZ50IIは適しています。4K/60p・10bit記録、N-Log・HLG対応といったプロ向け仕様が標準搭載されており、色の階調や編集耐性が格段に向上します。商品レビュー用の「商品レビューモード」なども備えているため、レビュー系動画との相性も抜群です。
さらに、今後さらに写真や動画スキルを伸ばしていきたいと考えている方にも、Z50IIは安心して使い続けられる1台です。AF精度や処理速度といった基本性能が大幅に強化されており、成長に合わせて機材側がボトルネックになりにくいのは大きな利点です。
一方で、日常の記録用途や旅行スナップ中心で、現在のZ50の性能に特に不満がない場合は、Z50を使い続ける選択肢も十分に理にかなっています。特に静止画中心であれば、Z50の軽さ・価格・操作性は今でも魅力的です。
つまり、乗り換えを検討すべきかどうかは、「現状の撮影スタイル」と「これから挑戦したい表現」によって決まります。性能を活かせる環境であればZ50IIは強力な選択肢となりますが、そうでない場合はZ50の継続使用がコスト的にも優れた判断と言えるでしょう。
Z50の生産は中止されるのですか?に関する回答
ニコンは2024年11月8日、公式サイトにてAPS-Cミラーレスカメラ「Z50」および関連キット製品の生産終了を正式に発表しました。これは、すでに2024年7月18日に受注一時停止が告知されていた内容の続報であり、Z50シリーズが市場から姿を消すことが明確になったかたちです。
今回、生産終了が発表された製品は以下の通りです。
- Z50(ボディ)
- Z50 16-50 VR レンズキット
- Z50 ダブルズームキット
この発表により、Z50は約5年間にわたる役目を終え、後継機Z50IIへの完全な移行が事実上確定しました。Z50は2019年に登場し、軽量・高画質・手頃な価格帯というバランスの良さから、多くの入門者や中級者に支持されてきたモデルです。その存在感の大きさを考えると、今回の発表は一つの時代の区切りとも言えるでしょう。
なお、ニコンは生産終了について「製品をお待ちいただいているお客様ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と正式にコメントしています。
今後はZ50IIがAPS-C Zマウントの中核モデルとして位置づけられることになります。Z50と同等の操作性を維持しつつ、AF・動画・処理性能が大幅に進化したZ50IIは、現在すでに販売が開始されており、Z50からのステップアップを検討するユーザーの注目が集まっています。
Z50の中古市場も今後活発になることが予想されますが、新品としてのZ50を購入できる機会は残りわずかです。検討中の方は在庫状況を早めに確認することが推奨されます。
ニコン Z50後継機とZ50を賢く使う方法
ニコン Z50は、軽量ボディと高画質を両立したAPS-Cミラーレスとして、多くのユーザーから支持を集めてきた名機です。使いやすさとコストパフォーマンスに優れ、初心者から中級者まで幅広く愛用されています。しかし、Z50には手ブレ補正非搭載やカードスロット1基などの注意点も存在し、購入や運用には理解が必要です。
本記事では、Z50の売れ行きや中古市場でのポイント、欠点とその補い方、さらにおすすめアクセサリーや人気レンズまで、Z50を最大限に活かすための情報を網羅的に解説します。
Z50の欠点は何ですか?注意点を解説
ニコン Z50は優れた性能を持つミラーレスカメラですが、いくつかの欠点もあります。あらかじめ理解しておくことで、後悔のない選択がしやすくなります。
まず、ボディ内手ブレ補正(IBIS)が非搭載である点は注意が必要です。これにより、手ブレ対策はレンズ任せとなり、暗所撮影や望遠撮影時には撮影者の工夫が求められます。
さらに、SDカードスロットが1つしかないため、バックアップを同時に取ることができません。仕事での使用や大切な撮影シーンではリスク管理が必要です。
加えて、タッチ操作やメニュー画面のインターフェースは、人によっては使いにくく感じることもあります。特に初めてのミラーレス機では、慣れるまでに時間がかかるかもしれません。
Z50の売れ行きと人気の理由とは
ニコン Z50は発売から数年が経過しているにもかかわらず、今なお根強い人気と安定した売れ行きを維持しています。その理由は、価格と性能のバランスに優れている点に加え、Zマウント対応という将来性のある設計にあります。
実際、ヨドバシカメラやMap Cameraといった大手カメラ販売店の販売ランキングでは、Z50シリーズが長期間にわたり上位を維持していました。特に「Z50 ダブルズームキット」は初心者向けモデルとしても高い人気を誇り、2024年にZ50IIが登場した後も、Z50の評価が下がることはありませんでした。
この人気を支える要因の一つは、約450gという軽量コンパクトなボディと、高画質を実現する2088万画素APS-Cセンサーの組み合わせです。小型ながらもしっかりとした描写が可能であり、旅行や日常スナップなど、荷物を抑えたい撮影スタイルに適しています。
また、レンズキットとして提供される「16-50mm VR」レンズも高評価です。広角から標準域をカバーできるこのレンズは、「カメラ初心者でも撮りたいものがだいたい撮れる」との声が多く、実用性の高いセットとして好まれています。
さらに、中古市場でもZ50は価格の安定性が高く、再販価値が落ちにくいことも評価されています。新品の流通が減ってきた今、中古でも手が届きやすい価格帯を維持している点は、予算を抑えて始めたいユーザーにとって大きな魅力です。
一方で、2024年に後継機となるZ50IIが登場したことにより、Z50は生産終了となりました。それでも「軽さ」と「操作性」に魅力を感じる層にはZ50の方が合っているというレビューも多く、Z50IIへの乗り換えを検討する中でもZ50の人気は依然として健在です。
このように、ニコン Z50は高画質・小型・手ごろな価格を兼ね備えたバランスの良いモデルとして、長期間にわたって高い評価を維持しています。後継機が登場した今も、Z50は「買って損のないカメラ」として、多くの人に選ばれ続けているのです。
ニコン Z50 中古市場で買うときのポイント
中古でニコン Z50を購入する際は、いくつかの確認ポイントを押さえておく必要があります。これにより、状態の良い個体を選ぶことができ、長く快適に使用できます。
まず確認したいのは「シャッター回数」です。Z50は電子シャッターと機械シャッターの両方を使用できますが、総シャッター回数はカメラの使用歴を知る重要な手がかりになります。
次に、ボディや液晶画面に目立つキズやスレがないかもチェックしましょう。特に液晶部分はタッチ操作を多用するため、摩耗しやすいポイントです。
また、ファームウェアが最新の状態であるかどうかも確認しておくと安心です。古いバージョンだと不具合が残っている場合もあるため、購入後にアップデートできるかも含めて確認しましょう。
Z50のおすすめアイテムで撮影を快適に
ニコン Z50は軽量コンパクトなAPS-Cミラーレスとして定評がありますが、撮影環境や用途に応じたアクセサリーを加えることで、操作性・表現力・撮影効率が格段にアップします。ここでは、最新の周辺機器の中から「Z50に最適なアイテム」を厳選して紹介します。
■ 1. 予備バッテリー&USB充電器
Z50のバッテリー(EN-EL25)は1回の充電で約300~350枚の撮影が可能ですが、動画や外出先での長時間撮影には明らかに足りません。
- Nikon EN-EL25(純正)
→ 安定性・信頼性に優れ、純正チャージャーとの互換性も安心
→ 「バッテリー残量が読める」などファームウェア連携も魅力 - Neewer EN-EL25(1600mAh互換バッテリー)
→ 容量が純正より約20%増。コスパに優れたサブバッテリーに最適
→ 安心の過電流保護・過熱防止機能付き - Nitecore UNK2(デュアルUSB急速充電器)
→ 2本同時充電+USB-C対応。外出先でもモバイルバッテリーで給電可能
→ 電圧・充電状態をモニターできるLCD画面搭載
🔍 ポイント:Z50はUSB給電非対応のため、交換式のバッテリー運用が基本。予備2本以上が推奨です。
■ 2. ミニ三脚(手ブレ対策・Vlog対応)
Z50はボディ内手ブレ補正(IBIS)を搭載していないため、手ブレ防止のためにも三脚は重要です。
- Manfrotto PIXI ミニ三脚
→ 世界中のVloggerやカメラマンに愛用されているベストセラーモデル
→ 耐荷重1kg・滑り止め付きで、Z50+標準ズームの運用に最適
→ ボタン1つで角度調整でき、低位置撮影や自撮りにも対応
🔍 ポイント:軽量(190g)かつ耐久性が高いため、旅行や屋外撮影でも持ち運びが苦になりません。
■ 3. ワイヤレスリモコン(自撮り・手ブレ防止)
Z50はBluetoothリモコンに対応しており、遠隔でのシャッター操作が可能です。
- JJC ML-L7 互換リモコン
→ 純正「ML-L7」と同等機能で、1/2の価格
→ シャッター・動画開始・ズーム操作にも対応(対応レンズ時)
→ 旅行・集合写真・テーブル撮影などで構図を崩さず撮れる
🔍 ポイント:特に夜景やタイムラプス撮影では、カメラに触れずにシャッターを切れることが大きな利点になります。
■ 4. 外部マイク(動画の音質向上)
Z50はマイク端子付きのため、内蔵マイクより高音質な録音が可能です。
- RODE VideoMicro II
→ ショックマウント構造で雑音や接触音を大幅カット
→ 超軽量(40g)でZ50とのバランスも良好
→ デッドキャット(風防)付属で屋外でもクリアな音質
🔍 ポイント:Z50の動画性能を活かしたいなら、外部マイクの導入は必須といえます。
■ 5. NDフィルター(動画・長秒露光に)
Z50は絞り優先やシャッター速度を積極的に活用できるため、NDフィルターは表現力を高める鍵になります。
- Kenko バリアブルNDX II
→ 可変式でND2〜ND450相当まで対応(光量1/2〜1/450)
→ ガラス品質が高く、色かぶりや解像度低下が起きにくい設計
→ 動画撮影・日中のスローシャッター撮影に重宝
🔍 ポイント:レンズ口径に合わせてサイズを選ぶ必要があります。
■ 6. LEDライト(暗所・商品撮影に)
Z50は高感度耐性が高いですが、自然光が足りない場面では照明が必要です。
- Ulanzi VL49 RGB
→ 明るさ・色温度・色相(RGB)を自在に調整可能
→ 内蔵バッテリー式で連続撮影約2時間
→ 1/4ネジ対応で三脚やカメラシューマウントに取付けOK
🔍 ポイント:料理・小物撮影・ポートレートなど幅広く活躍。光の質にこだわりたい人におすすめです。
■ 7. カメラストラップ(長時間撮影の快適さ)
Z50は軽量ですが、長時間首にかけていると疲れやすくなります。
- Peak Design スライドライト
→ 幅広&柔らかい素材で肩や首への負担を軽減
→ アンカーリンクで脱着が簡単、バッグへの収納もスムーズ
→ 長さ調整が片手で即座に可能
🔍 ポイント:登山・旅行・イベント撮影など「動きながら撮る」スタイルに最適です。
●自分の撮影スタイルに合わせて選ぼう
| 撮影スタイル | おすすめアイテム例 |
|---|---|
| 長時間・旅行撮影 | バッテリー / 急速充電器 / ストラップ |
| 動画・Vlog撮影 | 外部マイク / 三脚 / NDフィルター / リモコン |
| 商品・物撮り・ポートレート | LEDライト / NDフィルター / ミニ三脚 |
| 自撮り・集合写真 | リモコン / ミニ三脚 / ストラップ |
Z50の弱点を補い、強みを最大限に活かすためには、適切な周辺機器を組み合わせることがポイントです。必要な場面で「ちょうど良い道具」が揃っていれば、撮影がもっと快適に、そして楽しくなります。
Z50の神レンズと呼ばれる人気レンズ紹介
Z50で真価を発揮する「神レンズ」は多数ありますが、撮影ジャンルや重視する性能によってベストな1本は変わってきます。ここでは、Z50ユーザーから評価の高い人気レンズを、性能・使いやすさ・画質面からご紹介します。
NIKKOR Z 35mm f/1.8 S(標準レンズの名作)
- 焦点距離:35mm(APS-C換算で約52mm)
- 開放F値:f/1.8(9枚羽根の円形絞り)
- 最短撮影距離:0.25m
- 重量:約370g
- 特長:優れた解像力と自然なボケ味、ナノクリスタルコートによるフレア抑制
- 推奨用途:日常スナップ、風景、自然なポートレート
画面全体でシャープな描写を保ちつつ、背景を自然にぼかせる理想的な標準レンズ。Z50に装着すると肉眼に近い視野感覚で撮影できます。
NIKKOR Z 40mm f/2(軽量で万能な1本)
- 焦点距離:40mm(APS-C換算で約60mm)
- 開放F値:f/2
- 最短撮影距離:0.29m
- 重量:約170g
- 特長:非常に小型軽量で、AFも静か。コスパも優秀
- 推奨用途:日常撮影、旅行、Vlog、自撮り
手のひらサイズでZ50とのバランスも抜群。旅行や日常用の常用レンズとして最適です。
NIKKOR Z DX 18‑140mm f/3.5‑6.3 VR(万能ズーム)
- 焦点距離:18–140mm(35mm換算で27–210mm)
- 手ブレ補正:最大5段分のVR効果
- 最短撮影距離:0.2m(ワイド端)
- 重量:約315g
- 特長:広角〜望遠まで1本で対応。手ブレ補正付きで動画にも有効
- 推奨用途:旅行、風景、運動会、家族イベント
とにかく1本で済ませたい人に最適なレンズ。明るさは控えめですが、手ブレ補正で補えます。
NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR(コンパクトズーム)
- 焦点距離:16–50mm(35mm換算で24–75mm)
- 手ブレ補正:4.5段分のVR
- 重量:約135g
- 特長:パンケーキスタイルの超小型設計、ズームレバー付きで操作性良好
- 推奨用途:日常スナップ、街歩き、Vlog
Z50の標準キットに採用されるだけあり、携帯性と扱いやすさに優れています。屋外スナップや日常記録にぴったり。
NIKKOR Z 50mm f/1.8 S(ポートレートにも使える高解像)
- 焦点距離:50mm(APS-C換算で約75mm)
- 開放F値:f/1.8
- 特長:ピント面のシャープさと背景のとろけるようなボケを両立
- 推奨用途:ポートレート、静物、背景をぼかした撮影
Z50でもフルサイズ画質に迫る描写が得られ、人物撮影をメインにする方に強くおすすめできます。
Viltrox AF 16mm F1.8 Z(超広角の高コスパモデル)
- 焦点距離:16mm(APS-C換算で約24mm)
- 開放F値:f/1.8
- 重量:約550g
- 特長:風景・星景・室内撮影に活躍する大口径広角。AFもスムーズ
- 推奨用途:風景、建築、夜景、星空撮影
純正に匹敵する解像力を持ちつつ、価格は半分以下という驚異的なコストパフォーマンス。広角好きにおすすめ。
Viltrox AF 56mm F1.4 Z(コスパ最強のポートレート)
- 焦点距離:56mm(APS-C換算で約84mm)
- 開放F値:f/1.4
- 重量:約290g
- 特長:被写体を浮き上がらせるような大きなボケと高い解像力
- 推奨用途:ポートレート、スナップ、暗所撮影
Z50ユーザーにとって、F1.4という明るさは大きなアドバンテージ。価格を抑えつつ本格的な表現ができます。
●用途別おすすめレンズまとめ
| 用途 | レンズ例 |
|---|---|
| 日常スナップ・万能 | Z 35mm f/1.8 S / Z 40mm f/2 |
| ポートレート | Z 50mm f/1.8 S / Viltrox 56mm F1.4 |
| 旅行・記録系 | Z DX 18-140mm / Z DX 16-50mm |
| 風景・建築・星空 | Viltrox 16mm F1.8 |
Z50はAPS-Cながらレンズ次第で表現の幅が大きく広がります。自分の撮影スタイルに合ったレンズを選ぶことで、カメラの性能を最大限に引き出すことができます。選ぶ基準としては、焦点距離・明るさ(F値)・サイズ・重さを総合的に判断することがポイントです。
Z50の設定とアプリで撮影がもっと楽しく
Z50は、設定と連携アプリを工夫することで、より便利に楽しむことができます。基本の撮影スタイルに合わせたカスタマイズが鍵になります。
例えば、Fnボタンに「ISO感度変更」や「AFモード切り替え」を割り当てると、撮影中の操作がスムーズになります。これにより、瞬時に環境変化に対応できるようになります。
また、ニコン公式の「SnapBridge」アプリを使えば、スマートフォンへの自動転送やリモート撮影が可能になります。特に旅行中やSNSへの即時アップロードを行いたいときには非常に便利です。
ただし、アプリの接続が不安定になることもあるため、使用前にBluetooth設定やアプリのバージョンを確認しておくとトラブルを防げます。
●アプリのインストールはこちらから(Android版)
●アプリのインストールはこちらから(iPhone版)
ニコン Z50後継機「Z50II」の進化ポイントと注目すべき特徴まとめ
本記事のまとめを以下に列記します。
- 画像処理エンジンがEXPEED 6からEXPEED 7へと進化
- 連写性能が約11コマ/秒から最大30コマ/秒に向上
- プリリリースキャプチャ機能で決定的瞬間の撮影が可能
- 被写体認識AFが9種類に対応し、動体追従性能が大幅に強化
- 4K/60p・10bit記録やN-Logなど動画機能が本格仕様に進化
- USB-Cによる給電・充電対応で運用の自由度が向上
- 商品レビューモードやImaging RecipeなどVlog向け機能が充実
- ファインダーや液晶モニターの視認性・操作性が強化
- ボディ内手ブレ補正は非搭載のまま軽量性を維持
- EN-EL25aバッテリー対応により実用性がわずかに向上
- サイズと重量はZ50よりやや増加し、約495gの本体重量
- 静止画・動画どちらにも対応するバランスの取れた性能
- 初心者からステップアップするユーザーに最適な選択肢
- 価格はボディ単体で約14万円、レンズキットで約16万円前後
- Z50は生産終了となり、Z50IIがAPS-Cの主力モデルに移行





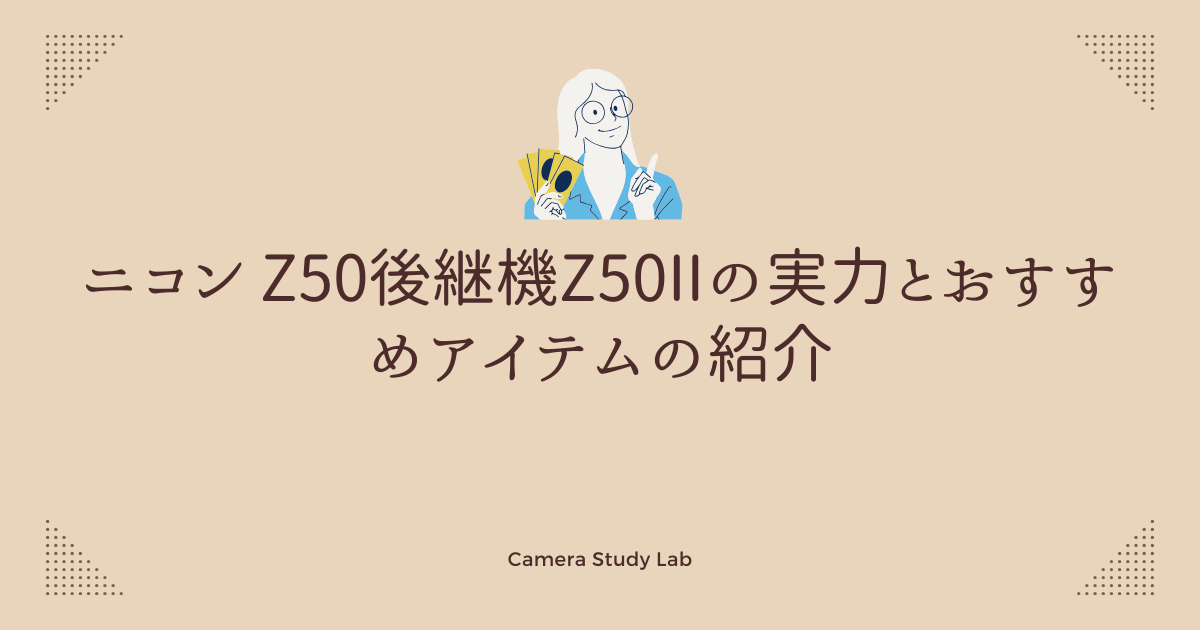
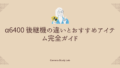
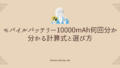
コメント