「Nikon Z5後継機は?」と検索している方の多くは、「Z5から買い替えるべきかどうか」「Z5IIの進化は本当に必要なのか」といった疑問を抱えているのではないでしょうか。この記事では、Z5ユーザーやこれから購入を検討している方に向けて、Z5とZ5IIの違いを丁寧に解説していきます。
Z5は高画質とコストパフォーマンスに優れたフルサイズ機として多くの支持を集めてきましたが、一部では「Nikon Z5 後悔」といった声や、「なぜNikon Z5は売れないのか」といった市場動向への関心も見られます。さらに、Z5が「Nikon Z5 プロカメラマン」たちにどのように評価されているのかも気になるポイントです。
この記事では、Z5IIという進化系モデルの実力や、どんな人に向いているのかを用途別に比較しながら、Z5の価値を改めて見直します。後悔しないための判断材料を、客観的かつ実用的にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
- Nikon Z5とZ5IIの具体的な違いと進化点
- 自分に合ったモデルの選び方と用途別の適性
- Z5IIの価格帯や競合機との比較ポイント
- プロや一般ユーザーによるZ5の評価と活用例
Nikon Z5後継機Z5IIは何が進化した?
Nikon Z5およびZ5IIは、フルサイズセンサーを搭載したミラーレス一眼カメラとして、エントリーユーザーから中級者、さらには静止画・動画をバランスよく楽しみたい層まで、幅広いニーズに応えるシリーズです。Z5は初めてフルサイズを手にしたい方にとって、価格と画質のバランスに優れた“入門機の完成形”ともいえる存在。
一方、Z5IIは画像処理エンジンやAF性能、動画機能が強化されており、「静止画も動画も本格的に取り組みたい」という方に適した進化版です。本記事では、両モデルの特徴や違い、選び方のポイントまで詳しく解説します。
Nikon Z5とはどんなカメラ?

Nikon Z5は、フルサイズセンサーを搭載したミラーレス一眼カメラで、NikonのZシリーズの中でもエントリーモデルに位置づけられています。主にカメラ初心者から中級者を対象としており、手頃な価格帯ながらフルサイズならではの高画質と描写力を体感できます。
搭載されているのは、有効画素数約2432万画素のCMOSセンサーです。これにより、細部までしっかりとした解像感のある写真が撮れる点が魅力です。また、5軸手ブレ補正やデュアルスロット(SDカード2枚対応)といった上位モデルに近い仕様も備えています。
これらの特徴から、Nikon Z5は「フルサイズで写真を始めたい人」や「コスパ重視の撮影愛好家」にとって非常にバランスの良い選択肢といえるでしょう。
ここで、Nikon Z5の主なスペックを表で整理してみます。
| 項目 | スペック内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2020年8月28日 |
| センサーサイズ | フルサイズ(35.9×23.9mm CMOSセンサー) |
| 有効画素数 | 約2432万画素 |
| 映像処理エンジン | EXPEED 6 |
| ISO感度 | 100~51200(拡張で50〜102400相当) |
| 手ブレ補正 | 5軸ボディ内手ブレ補正搭載 |
| オートフォーカス | ハイブリッドAF(コントラスト+位相差) |
| AF測距点数 | 273点(撮影範囲の広範囲をカバー) |
| 連写性能 | 約4.5コマ/秒 |
| 動画性能 | 4K/30p(※1.7倍クロップ)、フルHD/60p対応 |
| 記録メディア | SDカード×2(UHS-II対応) |
| モニター | 3.2型チルト式タッチパネル(104万ドット) |
| ビューファインダー | 約369万ドット 有機EL電子ファインダー |
| バッテリー駆動枚数目安 | 約470枚(CIPA準拠) |
| ボディ重量(バッテリー含む) | 約675g |
このように、Z5は必要十分な基本性能を備えつつ、堅牢性や操作性も配慮された設計となっています。高性能すぎず、かといって妥協点も少ないため、初めてフルサイズに挑戦するユーザーにとっては「ちょうど良い」存在といえるでしょう。
さらに、Zマウントシステムの恩恵として、高性能なS-Lineレンズとの相性も良く、ステップアップを視野に入れた長期的な機材選びにも適しています。
Nikon Z5の後継機 Z5IIが登場

Nikon Z5IIは、2024年4月25日に発売されたZ5の後継機種です。前モデルの魅力を受け継ぎつつ、処理性能や動画機能を中心に進化を遂げています。
注目すべきは、新しい画像処理エンジン「EXPEED 7」の搭載です。これにより、AF性能が向上し、動きの速い被写体にもより正確に追従できるようになりました。また、動画撮影では4K 60p記録に対応し、より滑らかな映像表現が可能です。
これまでのZ5が静止画に強みを持っていた一方で、Z5IIは「静止画も動画も1台で楽しみたい」というニーズに応えるモデルへと進化しています。
Z5IIで進化した主なポイントは次の通りです:
- 画像処理エンジンがEXPEED 6 → EXPEED 7に進化
- オートフォーカスの性能が大幅向上(人物・動物・乗り物検出AF対応)
- 動画性能が向上し、4K 60p対応(Z5は4K 30pまで)
- 最大連写速度が約4.5コマ/秒 → 約6コマ/秒に向上
- 電子シャッターでの静音撮影・無音連写が可能に
これらの改良により、Z5IIは「趣味の写真撮影だけでなく、動画撮影やVlogにも挑戦したい」という幅広い層にフィットする仕様になっています。
以下に、Z5IIの主なスペックを一覧にまとめました。
| 項目 | Nikon Z5II スペック内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2024年4月25日 |
| センサーサイズ | フルサイズ(35.9×23.9mm CMOSセンサー) |
| 有効画素数 | 約2432万画素 |
| 映像処理エンジン | EXPEED 7(Z8やZ9と同じ世代) |
| ISO感度 | 100~51200(拡張:50〜204800相当) |
| 手ブレ補正 | 5軸ボディ内手ブレ補正 |
| オートフォーカス | 被写体認識AF(人物・動物・乗り物対応) |
| AF測距点数 | 273点 |
| 連写性能(メカ) | 約6コマ/秒 |
| 連写性能(電子シャッター) | 最大20コマ/秒(JPEG撮影時) |
| 動画性能 | 4K/60p(フル画角)、FHD/120p対応 |
| 記録メディア | SDカード×2(UHS-II対応) |
| モニター | 3.2型チルト式タッチパネル(104万ドット) |
| ビューファインダー | 約369万ドット 有機EL電子ファインダー |
| バッテリー駆動枚数目安 | 約470枚(CIPA準拠) |
| ボディ重量(バッテリー含む) | 約680g |
こうして見ると、Z5IIは処理速度・被写体認識・動画性能といった現代のニーズに直結する要素がしっかり強化されていることがわかります。
いずれにしても、「Z5では少し物足りなかった点」を丁寧に補強したアップデートモデルであり、バランスと価格の両面で評価される1台になりそうです。今後、Zマウントユーザーの新たなスタンダード機として広がっていくことが期待されます。
NikonZ5とZ5IIの違いは?比較で考える
Z5とZ5IIの主な違いをスペック比較から考察します。
Nikon Z5とZ5IIの比較表
| 項目 | Nikon Z5 | Nikon Z5II | Z5IIが向上しているスペック(↑マーク) |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2020年8月 | 2024年4月 | - |
| 画像処理エンジン | EXPEED 6 | EXPEED 7 | ↑ |
| センサーサイズ | フルサイズ(2432万画素) | フルサイズ(2432万画素) | ― |
| ISO感度(標準) | 100〜51200 | 100〜51200 | ― |
| AF方式 | ハイブリッドAF (273点) | 被写体認識AF対応 (273点) | ↑ |
| AF被写体検出 | 非対応 | 人物・動物・乗り物に対応 | ↑ |
| 連写性能(メカシャッター) | 約4.5コマ/秒 | 約6コマ/秒 | ↑ |
| 連写性能(電子シャッター) | 非対応 | 最大20コマ/秒(JPEG時) | ↑ |
| 動画性能 | 4K/30p(1.7倍クロップ) | 4K/60p(フルサイズ) | ↑ |
| スロット数 | SDカード×2(UHS-II対応) | 同左 | ― |
| ボディ内手ブレ補正 | 搭載(5軸) | 搭載(5軸) | ― |
| ビューファインダー | 約369万ドット | 約369万ドット | ― |
| モニター | 3.2型タッチ・チルト液晶 | 同左 | ― |
| バッテリー駆動枚数(目安) | 約470枚(CIPA準拠) | 約470枚 | ― |
| 重量(バッテリー含む) | 約675g | 約680g | ― |
このように比較すると、Z5IIは画像処理性能、AF機能、動画機能、連写性能といったポイントで明確な進化を遂げています。Z5を気に入っていたユーザーにとっても、Z5IIはより万能なアップグレードモデルといえるでしょう。
NikonZ5IIのライバル機はどれ?
Z5IIのライバルとなるのは、主にCanonの「EOS R8」やSonyの「α7C II」など、フルサイズミラーレスの中でもミドルクラスに位置するモデルです。
これらの機種も価格と性能のバランスに優れており、高速AFや高画質動画、携帯性などを強みにしています。例えばEOS R8は軽量ながらもAF性能に優れ、動画にも強いモデルです。一方、α7C IIはコンパクトさを保ちながら上位機並みの画質を実現しています。
Z5IIは「静止画中心+動画も撮りたい」というユーザーにとって選びやすいモデルですが、動画性能や軽量性を重視するなら他社機種にも検討の余地があります。
それでは、スペック面での違いを具体的に見てみましょう。
| 項目 | Nikon Z5II | Canon EOS R8 | Sony α7C II | Z5II優位 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2024年4月 | 2023年4月 | 2023年10月 | ― |
| 有効画素数 | 約2432万画素 | 約2420万画素 | 約3300万画素 | ― |
| 画像処理エンジン | EXPEED 7 | DIGIC X | BIONZ XR | ― |
| AF被写体検出 | 人物・動物・乗り物 | 人物・動物・車・飛行機など | 人物・動物・昆虫など | ― |
| 連写性能(電子) | 最大20コマ/秒(JPEG)↑ | 最大40コマ/秒 | 最大10コマ/秒 | ↑ |
| 動画性能 | 4K/60p(クロップなし) | 4K/60p(クロップなし) | 4K/60p(6Kオーバーサンプリング) | ― |
| ボディ内手ブレ補正 | 5軸ボディ内手ブレ補正 | 非搭載 | 搭載(最大7段) | ↑ |
| ISO感度(標準) | 100~51200 | 100~102400 | 100~51200 | ― |
| ビューファインダー | 約369万ドット(OLED)↑ | 約236万ドット | 約236万ドット | ↑ |
| モニター | 3.2型 チルト式液晶 | 3.0型 バリアングル液晶 | 3.0型 バリアングル液晶 | ― |
| 記録メディア | SD×2(UHS-II対応)↑ | SD×1 | SD×1 | ↑ |
| ボディ重量(バッテリー込) | 約680g | 約461g | 約514g | ― |
| 市場価格(目安) | 約27〜30万円台 | 約23〜25万円台 | 約30〜33万円台 | ― |
Z5IIは特に以下の点でライバル機を上回っています:
- 連写性能(電子シャッター最大20コマ/秒)
- 5軸手ブレ補正の有無(EOS R8には非搭載)
- 高精細ファインダー(約369万ドット)
- デュアルSDカードスロット
これらは静止画撮影時の操作性や信頼性に直結するポイントです。動画や軽量性ではややライバル機に譲る場面もありますが、バランスの取れたオールラウンダーとしてZ5IIの立ち位置は非常に魅力的です。
撮影スタイルが「写真メイン+たまに動画」という方には、Z5IIは非常におすすめできる一台です。
NikonZ5IIのデメリットを冷静に検証
NikonZ5IIのデメリットを冷静に検証
Z5IIはZ5から多くの改良が加えられた、非常に完成度の高いフルサイズミラーレスです。しかし、すべての面で完璧なわけではなく、購入前に理解しておくべき注意点も存在します。ここでは、そのデメリットを冷静に整理しておきます。
●ボディ内手ブレ補正は据え置きレベル
Z5IIには5軸のボディ内手ブレ補正が搭載されていますが、Z5と比べて効果が大幅に強化されたわけではありません。動画撮影時や望遠レンズ使用時など、手ブレの影響を受けやすい場面では補正性能に限界を感じることもあります。
特に、手持ちで滑らかな映像を撮りたいと考えているユーザーにとっては、三脚やジンバルの併用を検討する必要があります。
●連写性能は標準的、上位機には届かず
Z5IIの連写性能は約6コマ/秒(メカシャッター時)、最大20コマ/秒(電子シャッター時/JPEG)と、前モデルからは確かに進化しています。ただし、これはあくまでミドルクラスとしての水準であり、Z8やZ9のようなプロ向け機と比較すると、動体撮影においては物足りなさを感じる場面もあります。
運動会や野鳥撮影など、動きの速い被写体を頻繁に撮影する目的であれば、さらなる上位機種の検討が無難です。
●タッチ操作の応答性に課題あり
一部ユーザーからは、液晶画面のタッチ操作に対する反応がやや鈍いという声も挙がっています。操作に少しラグを感じることで、撮影時のテンポが崩れると感じる人もいるようです。
特にスマートフォンのようなスムーズなUI操作を期待している方は、実機での操作感を事前に試しておくことをおすすめします。
●軽量性や携帯性では他社に一歩譲る
Z5IIは高い堅牢性を備えたボディ構造ですが、重量は約680gとライバル機よりやや重めです。Canon EOS R8(約461g)やSony α7C II(約514g)と比べると、長時間の持ち歩きや旅行用途では差を感じる場面もあるでしょう。
携帯性を最優先に考えている方にとっては、他社の軽量モデルの方が使いやすいかもしれません。
●被写体認識AFは対応範囲がやや限定的
Z5IIでは被写体認識AFが強化されましたが、対応しているのは主に人物・動物・乗り物までです。昆虫や鳥類の細かな検出まで対応しているSonyの上位AF性能と比較すると、認識対象の幅広さでは劣る部分があります。
より専門的なAF追従を求める方には、機能の幅や精度を比較した上で判断する必要があります。
●使用目的に合えば優秀、だが過信は禁物:Z5IIはバランスの取れたフルサイズ機であることに変わりはありませんが、万能ではありません。特に「動体撮影・軽量性・タッチレスポンス」などにこだわりがある場合は、事前に明確な使用目的と期待値を整理してから購入することが大切です。
写真も動画も楽しめる1台として十分魅力的な存在ではあるものの、「自分が求めるポイントで満足できるかどうか」は慎重に見極めておきましょう。
Z5IIの価格帯とコスパをチェック
Z5IIのボディ単体価格は22万円台〜30万円前後で推移しており、キットレンズ付きのセットモデルでも約35万円以内に収まるケースが多く見られます。
価格帯としては、初めてのフルサイズやサブ機として検討するにはやや高めの印象を持たれるかもしれません。しかし、画像処理性能や動画機能を考慮すると、同価格帯の競合機と比べても十分にコストパフォーマンスは高いといえます。
特に、写真も動画も高画質で撮りたいと考えるユーザーにとっては、バランスの取れた価格設定といえるでしょう。


Nikon Z5後継機もいいがZ5も十分良い理由
Nikon Z5は、フルサイズセンサー搭載のエントリーモデルとして、コストパフォーマンスに優れた魅力的なカメラです。しかし「安いフルサイズ」として注目される一方で、購入後にギャップを感じるユーザーの声も少なくありません。Z5が本当に自分に合った1台なのかを見極めるには、性能や機能だけでなく、使うシーンや目的を明確にすることが重要です。
本記事では、購入者の後悔や市場評価、プロからの視点、そしてZ5とZ5IIの違いやおすすめアイテムまで、実用目線で解説していきます。
Nikon Z5購入者の「後悔」とは
Nikon Z5は、手頃な価格でフルサイズの高画質を楽しめるミラーレス一眼として、多くのユーザーから支持を集めています。しかし、実際に購入した人の中には「思っていたのと違った」と感じるケースも存在します。ここでは、Z5購入後によく聞かれる“後悔の声”を紹介しながら、購入前に確認すべきポイントを整理していきます。
●動体撮影にはやや不向き
最も多く聞かれるのが、「動く被写体の撮影に弱い」という意見です。これは、Z5が搭載するオートフォーカス(AF)システムが最新機種と比べるとシンプルな構成であるため、動いている被写体を継続して正確に追従するのが苦手な傾向があるためです。
たとえば、スポーツ・子ども・ペット・野鳥など、すばやく動くものをメインに撮りたいと考えている方にとっては、思うような結果が得られず、物足りなさを感じる可能性があります。
●4K動画はクロップありで注意が必要
Z5は4K動画に対応していますが、撮影時に約1.7倍の画角クロップ(画面が狭くなる)が発生する仕様となっています。つまり、広角レンズを使っていても、思ったより画角が狭く感じられることがあるということです。
Vlogや風景撮影、インタビュー動画などで「フルサイズの広い画角を活かした映像を撮りたい」と考えていたユーザーには、やや制約となる仕様です。この点を知らずに購入すると、後から不満につながることもあるでしょう。
●タッチ操作が限定的
Z5にはタッチパネルが搭載されていますが、対応する操作がやや限られている点にも注意が必要です。
具体的には、メニュー操作のすべてをタッチで完結できるわけではなく、直感的にスマホのように操作したいと考える人にとっては、慣れるまで戸惑うこともあります。
撮影自体に大きな支障があるわけではありませんが、操作感にこだわる方には事前にチェックしておくことをおすすめします。
●購入後に後悔しないためには
Z5が悪いカメラというわけではありません。静止画メインで、風景・ポートレート・スナップをじっくり撮りたいという方にとっては、価格に対する画質や機能のバランスは非常に高く評価されています。
ただし、購入してから「思っていたのと違った」とならないためには、以下の点を購入前に整理しておくことが大切です。
- 動体撮影の頻度は高いか?
- 動画でフルサイズの画角を活かしたいか?
- タッチ操作やUIの快適さを重視するか?
これらの条件に強くこだわる場合は、Z5ではなく、AFや動画性能が強化されたZ5IIや、より上位のモデルを検討するという選択肢も視野に入れると良いでしょう。
Nikon Z5は、フルサイズ入門機として多くの魅力を持つ一方で、用途によっては不満を感じる部分があるのも事実です。後悔を防ぐためには、「自分が撮りたいもの」と「Z5の得意なこと」を照らし合わせて判断することが重要です。
目的に合った選択ができれば、Z5は非常に頼もしい1台として、長く活躍してくれるはずです。
なぜNikon Z5は売れないのか?
Nikon Z5が市場で他のモデルに比べて売れにくいとされる背景には、いくつかの要因があります。最も大きいのは、同価格帯に魅力的な競合モデルが多いという点です。
例えば、CanonやSonyといった他メーカーが軽量かつ動画性能に強い機種を展開しており、特に若年層や動画クリエイターの支持を集めています。一方で、Z5はどちらかといえば静止画向けの設計で、動画に強みがあるわけではありません。
このため、今のカメラ市場においてはニーズと若干ずれがある印象を受ける方もいるようです。
プロカメラマンはNikon Z5を使う?
Nikon Z5は、NikonのZシリーズの中でも「エントリーフルサイズ機」に分類されるモデルです。そのため、プロカメラマンが現場の主力機材としてZ5を使用する機会はそれほど多くありません。特に、報道・スポーツ・動物撮影など、厳しいスピードや堅牢性が求められるジャンルでは、Z9やZ8、あるいはZ6IIなどの上位機種が選ばれる傾向にあります。
ただし、すべてのプロがZ5を敬遠しているわけではありません。
●静物・風景・建築系のプロがサブ機として活用
Z5は約680gという比較的軽量なフルサイズボディでありながら、2432万画素の高精細な描写力と5軸手ブレ補正を備えています。このため、機動力と画質のバランスを重視する一部のプロカメラマンには、サブ機やロケ先の予備機として重宝されることもあります。
例えば、風景写真家の北村佑介氏は、自身のブログでZ5の描写力と操作性に言及しており、Z7IIと使い分けながら軽量撮影用の装備として活用していることを紹介しています。また、建築写真を手がける佐藤仁志氏は、狭い室内や三脚固定の撮影でZ5を使うことで、機材負担を減らしつつも高画質を担保できる点を評価しています。
●Zマウント資産を活かした選択肢として
Z5を選ぶプロの多くは、すでにZレンズを複数所有しているユーザーです。つまり、メイン機としてZ9やZ7IIを使用しつつ、「軽装でのスナップやロケ地の下見にはZ5を持ち出す」といった使い分けを行っているケースが多く見られます。
このような運用方法であれば、コストパフォーマンスの高いZ5は、プロにとっても実用的な選択肢となり得ます。
●動体・高負荷環境では力不足も
一方で、動きのある被写体を捉える必要があるスポーツフォトグラファーや報道現場で活動する写真家にとっては、Z5はやや性能不足です。
連写性能やAF追従の速度が上位機と比べて控えめであり、バッファも限られているため、「一瞬の勝負」に対応するには不安が残ります。実際、プロスポーツカメラマンの飯島裕氏は、Z5について「動体撮影には明らかに限界がある」と評しており、Z8やZ9のような連写と認識精度を備えた機材を勧めています。
Z5はその立ち位置から、プロカメラマンの“メイン機”として選ばれることは少ないのが現実です。しかし、使用ジャンルや役割を明確にすれば、十分にプロの現場でも活用される実力を持ったモデルです。
特に「軽量・高画質・シンプルな構成」を求める静物撮影や風景撮影の現場では、Z5の存在価値は明確です。Zマウントユーザーでコストを抑えつつ2台体制を検討している方には、サブ機としての導入も視野に入れてみる価値があるでしょう。
Nikon Z5はこんな人におすすめ!
Z5は、「写真をしっかり楽しみたいけれど、難しすぎる機能は必要ない」と感じている人に最適なカメラです。特に、静止画をじっくり撮影したい方にとっては、扱いやすさと高画質のバランスが魅力となります。
たとえば、以下のようなスタイルで撮影を楽しみたい方には、Z5が向いています。
- 風景やポートレートを落ち着いて構図して撮る
- カフェや街歩きのスナップを自然光で記録する
- 子どもやペットの「止まっている瞬間」を撮影する
- 画質にはこだわりたいが、動画はあまり使わない
このように、Z5は「静止画を丁寧に撮りたい人」にフィットする一台です。撮影に必要な基本機能はしっかり備えており、シンプルな構造ゆえに迷わず使いこなせる点も評価されています。
Nikon Z5IIはこんな人におすすめ!
Z5IIは、写真だけでなく動画にも本格的に取り組みたいと考える人に向いています。機能面の充実により、「静止画も動画も、どちらもクオリティを追求したい」というユーザーの期待に応えるモデルです。
特に次のような用途を想定している方には、Z5IIの選択が有力になります。
- 子どもの運動会やイベントで動きのある写真を撮る
- ペットや野鳥など、動きの読めない被写体を追いかける
- SNSやYouTubeなどで高品質な映像を発信したい
- 写真・動画どちらも重視し、将来の機材拡張も見据えている
Z5IIは、静止画性能の高さはそのままに、よりダイナミックな被写体やシーンにも柔軟に対応できる器用さを備えたモデルです。
用途別に考える、Z5とZ5IIの選び方
| 用途・目的 | おすすめモデル | 理由 |
|---|---|---|
| 写真を趣味として始めたい | Z5 | 操作がシンプルで、高画質な静止画撮影を楽しめる |
| スナップ・ポートレート・風景中心 | Z5 | 落ち着いた撮影に向き、軽快に持ち歩ける |
| 子ども・動物・動きのある被写体を撮りたい | Z5II | より速く正確なピント合わせができ、動体にも対応しやすい |
| 写真と動画を1台でこなしたい | Z5II | 動画機能が強化されており、映像作品や記録撮影にも活用できる |
| サブ機ではなく長期的に主力として使いたい | Z5II | 拡張性が高く、将来的な機材構成にも対応しやすい |
| 予算を抑えてフルサイズを体験したい | Z5 | 必要十分な性能を備えており、費用対効果の高いモデルとして支持されている |
Z5とZ5IIは、それぞれ異なる撮影スタイルや目的に合わせて選べるフルサイズミラーレスです。
Z5は「静止画をじっくり撮りたい初心者〜中級者」におすすめの、扱いやすくコスパに優れた1台です。一方、Z5IIは「動きのある被写体を狙いたい人」や「動画も積極的に活用したい人」にとって、頼れる多機能機種といえます。
あなたが「どんなシーンを、どう撮りたいか」を明確にすれば、どちらが自分に合っているかが自然と見えてくるでしょう。
Z5で十分という声は本当?
Z5は、静止画撮影を主とするユーザーにとって、今でも「十分な性能」を備えたフルサイズミラーレスです。価格と性能のバランスが取れており、満足度の高いカメラとして根強い人気を誇ります。
●フルサイズの高画質が身近になる
Z5の最大の魅力は、有効2432万画素のフルサイズセンサーによる高画質です。フルサイズならではの豊かな階調と立体感ある描写は、APS-Cセンサーのカメラとは一線を画します。
このセンサーにより、日常の風景やポートレート、夜景なども美しく撮影でき、撮って出しでも満足度の高い仕上がりが得られます。プリント作品やフォトブック作成にも十分対応できる解像力です。
●撮影時の安心感が高い
Z5は、撮影中のトラブルを防ぐための機能も備えています。デュアルSDカードスロットにより、同時記録やバックアップ撮影が可能で、大切な写真の保存に対する不安を軽減できます。
さらに、ボディ内5軸手ブレ補正があることで、三脚が使えない場面でも安定した撮影がしやすくなります。こうした基本性能の充実は、初めてのフルサイズユーザーにも安心感を与えてくれます。
●撮影スタイルの幅が広がる
Z5は、屋外・室内問わずさまざまな環境で対応しやすい設計になっています。視認性の高い電子ビューファインダーや、明るい屋外でも見やすい背面モニターなど、撮影時の操作性が良く、ストレスを感じにくい構造です。
これにより、風景・テーブルフォト・商品撮影など、多様なジャンルに柔軟に対応できます。持ち運びやすいサイズ感も、日常的に撮影する人にはありがたいポイントです。
●コストを抑えて高品質な環境を整えられる
Z5の価格はフルサイズ機としては比較的抑えられており、初期投資を抑えつつ高品質な写真体験を始めたい人に向いています。NikonのZマウントレンズは、豊富なラインナップと将来性があり、拡張性の面でも不安がありません。
カメラ本体と標準ズームレンズを組み合わせたキットであれば、手頃な価格で撮影を始められ、必要に応じてレンズを追加していくことも可能です。こうして段階的に機材を充実させる楽しみも得られます。
Z5は、静止画撮影を中心に楽しむユーザーにとって、性能・信頼性・コストのバランスに優れた1台です。とくに「初めてフルサイズを手にしたい」「写真を趣味として楽しみたい」と考えている方には、過不足のない性能を備えています。
このように考えると、「Z5で十分」という声には、明確な根拠があります。フルサイズ入門の1台として、今でも十分におすすめできるモデルです。
Nikon Z5におすすめのアイテム集
Nikon Z5をより快適に、より本格的に使いたい方に向けて、撮影の質や利便性を高めてくれる周辺アイテムを7つご紹介します。撮影スタイルに合わせて揃えることで、Z5の性能をさらに引き出すことができます。
1. マウントアダプター:Nikon FTZ II
Z5でFマウントレンズを活用したい場合は、このアダプターが最適です。装着することで、AF・AEが機能する対応レンズが多数あり、既存の一眼レフ資産を有効活用できます。前モデルよりも操作性が向上し、縦位置グリップとの干渉も軽減されています。
2. 純正予備バッテリー:EN‑EL15c
Z5の標準バッテリーと同型のEN‑EL15cは、予備として1〜2本持っておくと安心です。撮影枚数が多くなる旅行やイベント撮影では、予備バッテリーがあるだけで行動の自由度が増します。USB給電・充電にも対応しています。
3. 大容量互換バッテリー:NEEWER EN‑EL15c
コストを抑えて予備電源を確保したい場合、互換バッテリーも選択肢になります。NEEWER製などは純正とほぼ同等の容量(約2,400mAh)で、日常のサブ用として十分実用的です。充電器付きセットも多く販売されています。
4. レンズ保護フィルター:Kenko PRO1Dシリーズ
Zマウントレンズの前玉を傷や汚れから守るためのUVフィルターは、常用アイテムとしておすすめです。PRO1Dシリーズは、薄型設計でケラレを抑えつつ、光学性能も高水準。CPLタイプに切り替えれば、反射防止効果も得られます。
※レンズ径を事前に確認するようにしてください
5. カメラバッグ:Peak Design Everyday Backpack
Z5本体と交換レンズ、バッテリー、アクセサリーなどを安全かつ効率的に収納できるカメラバッグは必須アイテムです。Peak Designのバッグは耐久性・収納性・デザイン性に優れ、移動の多い撮影に最適です。
6. 外部マイク:RODE VideoMic Pro
Z5でVlogやインタビュー撮影をしたい場合、内蔵マイクでは音質に限界があります。RODEのショットガンマイクは、風切り音や環境ノイズを抑え、被写体の声や音をクリアに収録できるため、動画の完成度が大きく向上します。
7. カーボンファイバー三脚:Ulanzi 3028
Z5は高画質なセンサーを搭載しているため、三脚を使ったブレのない撮影がより映えます。Ulanziの軽量カーボン三脚は、持ち運びしやすく安定感もあり、風景・星空・長時間露光などに適しています。自由雲台タイプなら構図調整もスムーズです。
用途別おすすめアイテムまとめ
| 用途 | おすすめアイテム | 特徴 |
|---|---|---|
| Fマウントレンズを使いたい | FTZ IIマウントアダプター | Fマウント資産を活用しコスト削減が可能 |
| 長時間撮影・旅行に備えたい | EN‑EL15cバッテリー | 純正で安心、USB充電にも対応 |
| 予備電源を安価に用意したい | 互換バッテリー(NEEWER等) | 実用的な容量でコスパ良好 |
| レンズを常時保護したい | Kenko PRO1D UVフィルター | 傷・汚れ防止、光学性能も高い |
| カメラを安全に持ち運びたい | Peak Designカメラバッグ | 機材保護と機動力を両立 |
| 動画撮影の音質を高めたい | RODE VideoMic Proマイク | クリアな音質で編集がしやすくなる |
| ブレを防ぎ安定した撮影をしたい | カーボン三脚(Ulanzi 3028など) | 軽量かつ安定、星景や風景撮影に最適 |
これらのアイテムは、Z5の機能を最大限活用するための“相棒”ともいえる存在です。撮影スタイルに合わせて少しずつ揃えていくことで、より自由で快適なカメラライフが実現できます。
Nikonの新製品発表はいつある?
Nikonの新製品発表は、不定期で行われていますが、例年の傾向を見ると「春(2〜4月)」と「秋(8〜10月)」に集中する傾向があります。特にカメラ・レンズの発表は、国際的なカメライベントや展示会とタイミングを合わせて行われることが多いです。
今回のZ5IIも2024年4月に発表されており、この周期に沿ったリリースとなりました。今後の新製品情報を逃さないためには、公式サイトや信頼できるカメラメディアを定期的にチェックしておくのが有効です。
Nikon Z5とZ50の違いを徹底比較

Z5とZ50は、いずれもNikonのZマウントシステムを採用していますが、センサーサイズが大きな違いとなっています。Z5はフルサイズセンサー(FXフォーマット)を搭載し、Z50はAPS-Cセンサー(DXフォーマット)を採用しています。
その結果、Z5は階調表現やボケの美しさに優れており、画質重視の撮影に向いています。一方でZ50はコンパクトで軽量なボディが特徴で、気軽に持ち出して日常を撮るスタイルに適しています。
このように、用途と予算によってどちらが適しているかは変わりますが、Z5はより本格的な撮影を楽しみたい人向け、Z50は機動力を重視する人向けといえるでしょう。
関連記事:ニコン Z50後継機Z50IIの実力とおすすめアイテムの紹介
Nikon Z5後継機Z5IIの実力と特徴をまとめて解説
本記事のまとめを以下に列記します。
- Z5IIはZ5の正統進化モデルとして2024年4月に登場
- 画像処理エンジンがEXPEED 7に進化し処理速度が向上
- 被写体認識AFが追加され人物・動物・乗り物に対応
- 4K/60pの動画撮影が可能になり映像表現の幅が広がった
- 電子シャッターによる無音連写に対応し静音性が高い
- メカシャッターの連写性能も4.5コマ→6コマに向上
- バッテリー駆動枚数や基本設計はZ5とほぼ同等
- 写真と動画を1台でこなしたい層にとって最適な選択肢
- 動体撮影にも対応しやすくなり用途が広がった
- デュアルSDスロットや5軸手ブレ補正など信頼性も維持
- EOS R8やα7C IIといった他社の中級機と競合する立ち位置
- 静止画重視ならZ5、動画や動体重視ならZ5IIが選ばれやすい
- Z5IIは長く主力として使える拡張性を備えている
- 初めてのフルサイズとしてもZ5は依然として魅力的
- 用途や撮影スタイルに応じて明確な住み分けが可能





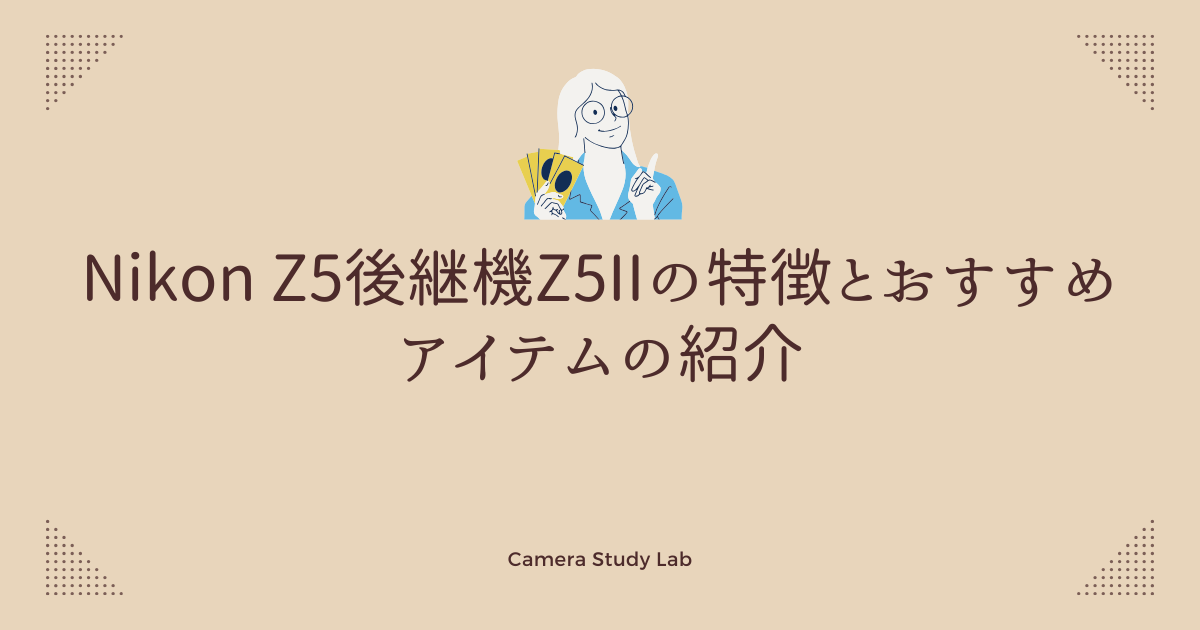
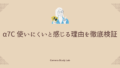
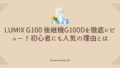
コメント